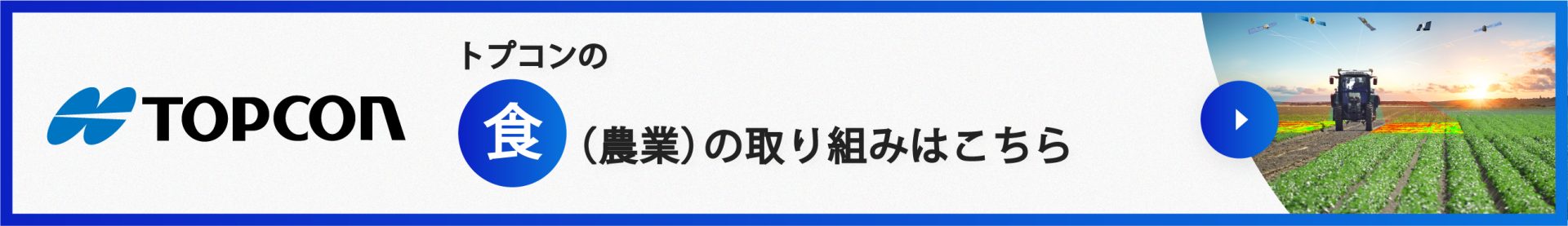目次
今や一度は食べてみたい高級米として知られる山形県発のブランド米「つや姫」。2023年3月に発表された2022年産の米の食味ランキングでも、つや姫は13年連続13回目の最高ランク「特A」を獲得しています。全国的にも高い人気と知名度を誇る山形県のブランド米ですが、近年は九州地方や中国地方など、西日本での栽培が増えてきました。そこで、つや姫の品種特徴や生産地が拡大している理由などを通し、人気品種が世代交代する今の時代の稲作農業について考察します。
人気が加速中の「つや姫」。その風味の特徴とは?
一般財団法人日本穀物検定協会が全国の産地から集まった品種を食味試験し、その評価を発表する「米の食味ランキング」。2023年3月に開催されたランキング評価で注目を浴びたのが、最高ランク「特A」を13年連続で獲得した山形県発のブランド米「つや姫」です。つや姫の人気の理由はといえば、その独特の食味にあり、他のブランド米でも甘みやうま味は当然ながら感じられるものの、つや姫はそれに加えて一度食べたらクセになる独特の粘りとコシの強さが特長です。
つや姫は山形県が総力を挙げ、10年かけた開発の末に満を辞して2010年に全国デビューした品種。誕生の背景には、米どころでもある山形県において、コシヒカリを上回る食味と知名度を誇る新たな米を作ろうという熱い思いからスタートしたことから、この長い年月かかかったのだとか。そんな苦労を重ねて誕生したブランド米だけに、今も生産者は一定の要件を満たし、認定された農家だけに限定して栽培適地で生産。また、品質確保のために山形県独自の出荷基準を設定し、それをクリアしたものだけを出荷するなど品質基準を徹底することでブランド力を高めています。また、つや姫は価格も年々高騰中で、現在は5kgを3,000〜4,000円台で販売(JAタウン公式サイトより)。最高級米として知られる魚沼産コシヒカリと並ぶ高値を維持しています。

山形県発のブランド米が西日本で拡大中
山形県が心血を注いで開発したつや姫ですが、調査によると近年は山形県だけでなく西日本にも栽培地が拡大中です。2024年産の山形県内のつや姫の作付面積は約1万100ヘクタール、宮城県が約5,000ヘクタールを栽培し、次いで島根県が約1,350ヘクタール、大分県は約700ヘクタールと、西日本の栽培地が目立ってきました。
西日本の最大栽培地である島根県では、2012年から県内約270ヘクタールでつや姫の本格栽培がスタート。約10年で5倍もの作付面積が増えています。また、大分県は2011年から103ヘクタールで栽培が始まり、約10年で7倍と年々増加傾向です。
また、米の品種別作付面積割合をみても、第1位はコシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリと、定番の品種が続くなか、つや姫は12位と健闘。米の銘柄は誕生した地域の近隣で栽培される事例はみられるものの(コシヒカリなど圧倒的な知名度を誇る品種を除く)、全国で栽培される例は珍しく、つや姫のように市場デビューしてわずか10年余りの米が各地で栽培される例はかなり珍しいといわれています。

全国的に拡大する理由は、高温耐性と価格の安定から
なぜ、デビュー間もないつや姫が全国で栽培地を広げているのか? その理由を探ると、近年の気候変動による米の品種転換が背景にありました。西日本においてつや姫の作付面積が最も多い島根県は山間部が多いことから、もともとは耐冷性のある「ひとめぼれ」や「コシヒカリ」の栽培が盛んな地域。しかし、近年は温暖化による高温障害の影響から、“シラタ”と呼ばれる白い未熟粒の発生が増加し、さらには台風による倒伏被害も増え、農家の頭を悩ませていました。
そこで注目されたのが、つや姫。つや姫は高温耐性があり、丈が短く倒伏しにくい品種であり、なおかつ食味の良さも評判なことから販売価格も安定しています。そこで、島根県では2012年からコシヒカリに替わる県奨励品種としてつや姫を推進し、本格栽培をスタート。つや姫へと切り替える農家も増え、栽培地が徐々に広がってきました。
しかしながら、つや姫は山形県内では徹底した管理下で栽培することでブランド力を維持しています。前述の通り、県内では認定を受けた農家しか生産ができず、出荷の際もタンパク質含有量など県独自の出荷基準を設けています。そこで山形県では県外産地においても栽培マニュアルを遵守して特別栽培基準の栽培管理を行うこと、有機JAS認証を取得することなどといった様々な条件を課すことで、栽培産地が拡大してもブランド力が低下しないよう努めています。また、山形県にとっても西日本で栽培が増えることでつや姫の認知度アップにつながるため、普及活動にも熱心に取り組んでいます。

米も人気品種が世代交代か?今後の稲作経営について
一昔前は人気の米の銘柄といえばコシヒカリが圧倒的な強さをみせていました。作付け比率は全品種の33.7%と、今も多くを占めていますが、ここにきて温暖化や気候変動による影響もあり、つや姫など今の環境に耐性がある新品種へと世代交代が始まっています。しかしながら、農家としては長年栽培してきた品種から新しい品種へ替えることは不安もあり、抵抗感が強いはずでしょう。しかし、収穫量を確保し、安定した農業経営を続けていく上で、品種の見直しを考える転換期かもしれません。
そして、新しい品種、新しい農作物を取り入れる農業の転換期に導入を検討したいのがスマート農業です。ICTを活用したスマート農業に取り組むことで、生産性の飛躍的な向上を実現し、人手の確保や負担の軽減なども実現してくれます。
トプコンでは「農業の工場化」を目指して、スマート農業の推進にいち早く取り組んできました。「自動操舵システム」は、位置情報によって農業トラクターのハンドリングを制御。事前に設定したコースに沿って手放しでも真っ直ぐに走れるようになります。肥料をまく可変施肥機と連動させれば、事前に作成したマップ通りに肥料をまくことも可能。しかも、これらの作業は農業の熟練者だけでなく、農業の未経験者でも無理なく行えるというメリットもあります。
スマート農業は農業での人手不足の解決、熟練技術の継承などにつながる可能性を明示しています。米の品種が時代とともに変化している今、これからの米づくりも大きく変わろうとしています。そこにスマート農業を導入することで、今後の米づくりを取り巻く問題を解決する一助になるのではないでしょうか。
トプコンは、2006年よりスマート農業に取り組んでいます。
〈参考資料〉
山形県HP「令和6年産「つや姫」生産者認定・生産計画の募集について」
農林水産技術会議「極良食味で炊飯米の外観が秀でた水稲品種「つや姫」の育成と普及」
島根県HP「島根県の新品種「つや姫」」
島根県HP「水稲・麦・大豆指導指針」
大分県HP「つや姫のページ」
米穀機構 米ねっと「令和4年産水稲の品種別作付動向について」