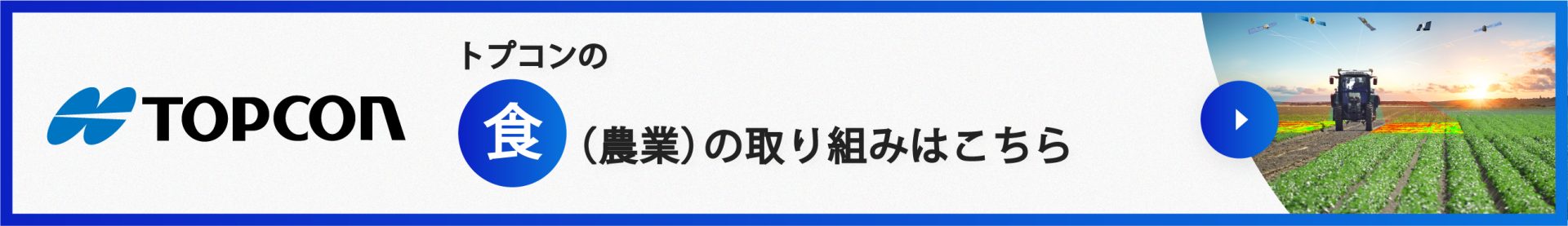目次
最近、花を買いましたか? というのも、日本では、花き(観賞用の植物のこと)消費が伸び悩んでいます。しかも、切り花の国内出荷量は、ピーク時である1996年の57億5,000本から、2022年は31億3,900万本までに減少。リーズナブルな切り花の輸入が増えたことも原因のひとつです。そのため、国は、花きの振興に関する法律を2014年に成立させたほどです。けれども、残念ながら現在も緩やかに減少中。花の生産者の経営を安定させることを目的として、国際競争力を強化するべく、様々な対策が講じられています。そこで、花き産業の現状と課題、希望について紹介しましょう。
コロナ禍のホームユース、サブスクで増加しても
花き産業が、新型コロナウイルスの感染拡大によって、歴史に残る程のダメージを受けたニュースは、記憶に新しいところです。一時は、冠婚葬祭、卒業式・送別会、イベント等の開催自粛により、消費全体の28%を占める業務用が、ほぼ0に。個人消費においても、お墓参り用の切り花が動かない等、生産者や花屋は、厳しい状況に立たされました。農林水産省が、家庭や職場に花を飾って楽しむことを促し、消費拡大を図る推進事業「花いっぱいプロジェクト」をスタートさせるまでに深刻な問題となっていたのです。
ところがここに来て、花のストレス軽減効果を潜在的に感じているのか、国の推進の甲斐あってか、ホームユースが増加。花き産業の少しの救いとなりました。それにともない、スーパーマーケットでの購入も増加。新型コロナウイルス感染症が5類相当に移行してからは、墓参りが急増したことで、2023年はスーパーマーケットでの購入割合(複数回答)が過去最高の40%となったという調査も出ています(日本農業新聞)。結果、花きの消費傾向は、パンデミック以前に戻りつつあるとのこと。
また、サブスク需要が堅調であることは、今後への期待が高まります。「花のEC・サブスク市場(一部鉢物を含む。切り花が大半を占める)は、2020年と2022年比で約3.5倍と急成長し、2023年には300億円の市場規模になると予想されます(大田花き推計)」(日本経済新聞2023/6/29より)とのことで、集計が気になります。今後は、若年層の消費が鍵となることから、サブスクを頻繁に利用する若年層が花を普段使いしやすくなるためのプロモーションが急がれます。

ちなみに、「フラワー需給マッチング協議会」が、従来の花の長さを10cm短くして約70㎝とする「スマートフラワー」という規格を作ったことも昨今の新たな動きといえます。豪華な花束よりも小さなブーケが好まれたり、スーパーマーケットからの「短くして欲しい」という要望が増えていたりと、ニーズの変化を捉えた結果です。こちらの「スマート」は、「無駄を無くす」という意味が込められているとのこと。
出荷量は約31億本。TOP3は、キク、バラ、カーネーション
そもそも日本でいう「花き」(漢字で書くと「花卉」)とは、「花きの振興に関する法律」の第二条で「観賞の用に供される植物をいう(法律ママ)」と定義されています。具体的には、切り花類、鉢もの類、花木類、球根類、花壇用苗もの類、芝類、地被植物類を言います。その内の6割が、切り花類です。
2022年の切り花類を国内出荷量で見ると、全体では31億3,900万本。キクが断トツに多く、12億2,700万本。キクの都道府県別出荷量割合は、愛知県が1位で、36%を占めています。愛知県は、1962年の昭和時代から花の産出額が日本一とあって「花の王国あいち」を名乗っているほどで、出荷本数は、全体の19%です。
2022年の切り花を出荷量の第2位は、バラ1億9,100万本、第3位は、カーネーション1億8,870万本。続いて、ガーベラ、スターチス、ユリ、トルコギキョウ、リンドウ(切り枝、切り葉を除く)。実は、世界の三大切り花も日本と同じく、キク、バラ、カーネーションです。

コロンビア産カーネーションが日本国内を席巻
数字だけで判断すると相当な数ですが、国内出荷量のピークは、1996年でした。その後は、減少の一途。原因の一つは、切り花の輸入増加です。例えば、カーネーションは、最も多く、2021年では65%が輸入に頼っているのです。輸入先は、半分以上がコロンビア。コロンビアは、コーヒーの国でもあり、同時に、世界の中の「花の王国」。オランダに次いで花の輸出量が二番目に多い国です。日本とは異なり、気温が一年を通して安定していることで、加温施設等が不要。生産コストを抑えられる、つまり安価であることが強みになっています。
そこで、国は、花き産業と花きの文化振興を図るため、「花きの振興に関する法律」を2014年に成立、施行させました。目的は、「花きの生産者の経営の安定、花きの加工及び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な発展と心豊かな国民生活の実現に寄与すること」(農林水産省「花き振興に関する法律のあらまし」より)。施行から、今年で10年。多くの推進事業が実施されたことで、成果も期待されています。

クオリティが高い日本の花は世界で愛される
日本の花き産業に希望がないのかというと、そうではありません。最たる希望は、海外にあります。日本の花の評価が、非常に高く、花きの輸出が好調なのです。2020年の切り花における輸出額は、前年より約14%増で15億円。多様な品種とクオリティの高さは世界も認めています。
世界で愛される主要な花は、長野県の「トルコキキョウ」。オランダで開催された国際園芸博覧会の切り花部門コンテストで世界一に輝きました。他に、アジアでの人気が高いのは、2020年から輸出を開始した福島県の「ダリア」。赤色と金色が特に人気です。2008年頃から輸出されているのは、北米で人気の宮崎県の「スイートピー」。高知県の「グロリオサ」は、赤い花が縁起良いと装飾用として中華圏向けに伸びています。花の大きさや茎の太さなどが評価され、コロンビア等で大量生産されていない品種が人気とのことです。
これらの輸出をさらに増やすことを大きな課題と捉える日本は、国際・産地競争力の強化に力を入れています。推進を図るために導入を急がれるのが、スマート農業。花き産業においても栽培農家が今後も減少することは明らかなため、ロボットやAI、IoTを活用しての労力削減、品質向上が求められていくとみられます。
日本の花を世界中に誇れる日が早く訪れることを心待ちに。トプコンは「農業の工場化」をコンセプトにDXソリューションを提供し、世界中の農家をサポートします。
〈参考文献〉
日本農業新聞「花購入4割がスーパー コロナ明け 墓参り用急増」
朝日新聞デジタル「豪華な花束より小さなブーケ 時代を映した新企画、生産地にも恩恵」
日本経済新聞「サカタのタネと大田花き、福島県・長野県にて共同でEC・サブスクリプション向けのトルコギキョウの商品仕様を開発」