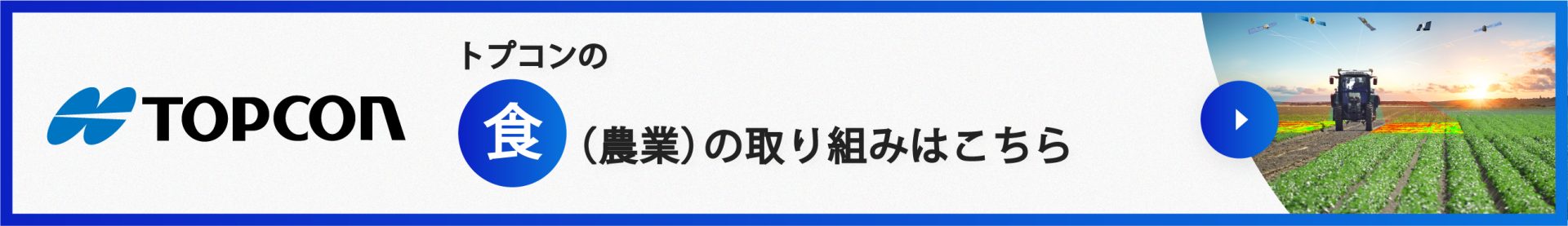目次
米のおいしさの評価する指標として知られる「米の食味ランキング」。最高評価の特Aの獲得をめぐっては、毎年多くの産地が一喜一憂し、消費者の購入動向にも大きな影響を与えています。今回は、2024年産米で特Aを獲得した注目の品種や評価の傾向とともに、おいしい米を栽培するためのヒントをお伝えします。
「令和6年(2024年)産米の食味ランキング」の結果
2025年2月に日本穀物検定協会は「令和6年(2024年)産米の食味ランキング(https://www.kokken.or.jp/ranking_area.html)」を発表しました。全国で生産された米の味や香り、粘りなどの評価するこのランキングは今年で54回目。この取り組みに、今回は各都道府県から選出された143産地品種が審査対象となりました。
◆令和6年(2024年)産米 特Aランク
北海道「ななつぼし」「ゆめぴりか」
青森県「はれわたり」
岩手県(県中)「銀河のしずく」
宮城県「つや姫」
秋田県「サキホコレ」、(県南)「あきたこまち」
山形県(村山・置賜)「つや姫」、(庄内・置賜)「雪若丸」
栃木県(県北)「コシヒカリ」
埼玉県(県西)「彩のきずな」
新潟県(魚沼)「コシヒカリ」
富山県「コシヒカリ」
福井県「いちほまれ」
長野県(北信・東信)「コシヒカリ」
岐阜県(美濃)「コシヒカリ」
静岡県(東部)「きぬむすめ」、(西部)「にこまる」
愛知県(三河中山間)「ミネアサヒ」
三重県(伊賀)「コシヒカリ」
滋賀県「みずかがみ」
兵庫県(県北)「コシヒカリ」、(県南)「きぬむすめ」
和歌山県(県北)「きぬむすめ」
鳥取県「きぬむすめ」
島根県「きぬむすめ」
岡山県「きぬむすめ」
山口県「きぬむすめ」
徳島県(南部)「コシヒカリ」
愛媛県「にこまる」
高知県(県北・県西)「にこまる」
佐賀県「さがびより」「夢しずく」
大分県(西部)「ひとめぼれ」
鹿児島県(県北)「あきほなみ」
最上級の「特A」評価を受けた産地品種は39で、前年より4つ減少して11年ぶりの少なさとなりました。「A」評価も76産地品種と前年から2つ減少しています。「特A」が減った最大の要因は、周知のとおり全国的に続いた猛暑です。特に収穫時期に残暑が厳しかった関西以西の地域では、白未熟粒や胴割れの発生による品質の低下評価を押し下げました。一方、北海道や東北、北陸地方は比較的天候に恵まれたうえ、高温対策に積極的に取り組んだ結果、前年よりも評価を上げた銘柄が増加。東西で明暗が分かれる結果となりました。

「米の食味ランキング」で選ばれた米は本当においしい?
「米の食味ランキング」は、一般財団法人日本穀物検定協会が良質米づくりの推進と米の消費拡大に役立てることを目的に実施しているものです。全国各地から集まった多くの産地・品種-を対象に食味試験を行い、その結果を毎年ランキングとしてとりまとめ公表しています。1971(昭和46)年産米から毎年発表されており、最上位の「特A」ランクは平成元年から設定されました。
食味試験では、白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目について、複数産地のコシヒカリをブレンドした基準米と比較されます。そして、専門の食味評価員が基準米よりも特に良好なものを「特A」、良好なものを「A」、基準米とおおむね同等のものを「A’」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B’」として5段階評価が行われ、ランキングとして発表します。
米の品質基準として、米の食味ランキング以外に「等級評価」もあります。等級評価は、数値を基準に米の見た目を重視する客観的評価が等級評価であり、一方の米の食味ランキングは、白米を実際に食べておいしさを審査する主観的評価です。こうした違いから、米の食味ランキングは、各地で誕生し栽培されているおいしい米の最新情報を知ることができる、貴重な機会となっています。
出品銘柄が減少した理由と、その中で存在感を示した高温耐性品種
今年の米の食味ランキングに選出された産地品種数は143で、昨年は144、さらに一昨年は152と、じわじわと減少傾向が続いています。背景には、出品の条件として一定以上の生産量があることが求められる一方、生産者の減少により、この条件を満たせない銘柄が増えてきていることがあります。さらに昨年は猛暑の影響による品質への不安から、出品を見送る産地もあり、選出数減少に拍車をかけたと考えられています。

こうした厳しい気象条件の中で、改めて存在感を示したのが高温耐性品種です。今回、高温耐性品種を出品したのは30県・39産地品種で、そのうち23産地品種が「特A」評価を獲得。全体の半数以上を占めるました。中でも注目は「きぬむすめ」です。岡山県産は9年連続で特Aを獲得し、「特A」評価を得た産地は前年の6から今年は7へと増加しています。また、青森県の「はれわたり」は2023年に全国デビューしたばかりの新品種でありながら、参考品種での出品を含め、3年連続で「特A」評価を獲得。さらに、山形県の「つや姫」は2025年産から5年間で1万トンの増産を計画するなど、今後の拡大にも期待がかかります。
これらの結果からも、高温耐性品種の重要性が高まっていることがうかがえます。今後の米づくりでは、暑さ対策が食味の質を左右する大きなカギとなるでしょう。

消費者による米選びの現状と今後の米づくりの取り組み
米の食味ランキングで特Aを獲得することは生産者にとっても大きな励みになるだけでなく、注目度や需要の拡大につながり、売り上げやブランドイメージの向上にも直結します。一方で消費者ニーズの多様化やライフスタイルの変化も伴い、環境に配慮して生産された米やこだわりの栽培方法の米などへの支持も高まっています。今後は食味の良さを追求した品種や高温耐性品種の栽培に加え、食味+αの魅力を備えた米づくりに着眼点を置くことが重要だともいえます。
こうした米づくりの現場で今注目を集めているのがスマート農業です。トプコンは、技術面や肉体的負担を軽減する「自動操舵システム」を開発し、農作業の省力化・効率化を実現しています。これにより、農業経験が浅い人でも熟練者並みの作業が可能となり、2006年の取り組み開始以来、現場の効率化と農業全体の持続的発展を支え続けています。
〈参考資料〉