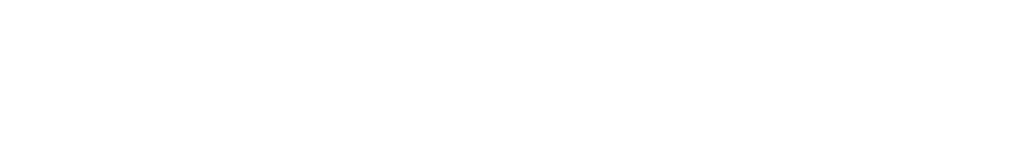目次
東京都板橋区本蓮沼に本社を構える株式会社トプコン。敷地内には、1932年(昭和7年)の創業期に完成した1号館から2000年代に建設された11号館まで、各時代の建築様式を採り入れた、興趣豊かな社屋たちが現存しています。
敷地内の景観は、さながら近代建築博物館。かつて長閑な田園風景が広がっていたこの地に、先達は何を思い何を夢見て、この高尚な社屋群を築いたのでしょう。その思いや夢は、現在のトプコンに何を残しているのでしょう。
今回は表情豊かな社屋をご紹介しながら、トプコンの歩んできた激動と飛躍の時代、そして今も受け継がれる《見えない資産》について考えます。

1937年の本社工場。手前右が1号館で、右奥が2号館
浪漫が仕事を楽しくした、田園風景の白亜の洋館
鉄筋3階建ての白い洋風建築。令和の私たちの目には、控えめで上品な佇まいと映ります。けれどこの1号館が完成した当時、周囲はフクロウの鳴く森や農家や牛舎が点在する一面の畑でした。突如現れたこの白亜の洋館は、どれほど周囲の人々の夢や憧れを誘い、社員の誇りを高めたことでしょう。
この建物の南側壁面には、洒落た円形の窓が1階から3階にかけて4つ並んでいます。実はこの内側は各階の男性用トイレ。中から外へ目をやってリフレッシュする時も、建物を見上げて外を歩く時も、窓が四角くないだけで自然と気持ちが和みます。またこの窓は、中心部に回転軸を設けた回転窓になっていて通気がしやすく、外側の窓ガラスが建物内側から容易に掃除できる利点も。装飾性と機能性と、ひとへの思いやりを両立した秀逸な意匠です。
室内を見ると、天井の梁は柔らかくアーチを描き、階段の手すりも角のない丸みを帯びたフォルムに仕上げられています。また建物1階の東側には、再び丸窓と、不思議な高さの入り口と、その扉の上には鉄製の装飾をあしらった明かり取り窓があります。心なしか、この1号館が建てられた頃のトプコンの社名、東京光学機械株式会社のTの文字を図案化したようにも見えますね。シンプルかつリズミカルな、洗練された幾何学デザインです。
 目にも優しい丸窓。ゆったりした時が流れていた時代の産物だ
目にも優しい丸窓。ゆったりした時が流れていた時代の産物だ
こうした設計やデザインは、1910年代半ばから1930年代にかけてフランスから全世界へ流行が広がった美術・工芸・装飾様式、アールデコの影響と考えられます。日本に現存するアールデコの名建築、旧朝香宮邸(現在の東京都庭園美術館)は、1号館とほぼ同時期の1933(昭和8)年に完成。ここでも、トプコンのものとよく似た、優美な丸窓を見ることができます。
 アールデコデザインの特徴である優雅な曲線美が見て取れる
アールデコデザインの特徴である優雅な曲線美が見て取れる
ちなみに。旧朝香宮邸の1年前に完成し、まもなく築90年を迎えるトプコン1号館が、本来の機能を失った観賞用の記念物ではなく、稼働する社屋として今も現役であるのは、特筆すべきことです。建物は、人がそこで営みを続けてこそ生命を保つのですから。
高揚と緊張と静かな祈りが共存する、新古典主義建築
次は、2号館へご案内しましょう。2号館は、1935年(昭和10年)に建物南側部分がコの字型に作られ、1937年(昭和12年)に北側の5階建て部分が増築されて、現在のロの字型になりました。この頃は軍需による好景気があり、毎年のように建物の増改築が行われていたようです。
2号館は、1号館とは明らかに趣が異なります。北側から見ると、まず目につくのは高い位置に大きく張り出した庇。地面から力強く垂直に立ち上がって庇を支える、太い柱の列……。これは、当時モダニズム建築と並んで流行していた、新古典主義建築を採り入れたもの。ファサードと呼ばれる建物正面にギリシャ神殿を思わせる列柱を持つのが特徴で、古代ギリシャやローマの建築要素がルーツと言われています。
新古典主義建築は、大手銀行など、信頼感を重んじる重厚な企業が好んで採り入れる傾向にあります。日本国内では、東京・日本橋の三井本館や二重橋前の明治生命館などが一例ですが、時代がくだると、マッカーサーの執務室が置かれた第一生命ビルのように柱の装飾が省かれ、次第にシンプルになっていきます。
2号館建設にあたってトプコンが、1号館のような洒脱で優しいアールデコ様式から離れ、威風堂々として荘厳な新古典主義建築を選んだのは、軍需に応える企業としての権威を重んじたのでしょうか。あるいは時代の趨勢、あるいはまた別な思いがあったのでしょうか。
2号館には、戦争の痕跡が今も残ります。戦時中、北東部の屋上の最も高い場所には、低空で侵入する敵機に対抗するための防空監視所が置かれ、高射砲も備えられていました。その台座は現在も残り、その下は1階から6階まで、床や天井を外して大きなものを屋上まで吊り上げられる構造になっています。一方、この2号館屋上には社内でここだけ、神社が鎮座しています。来訪者に何かを語りかけ、何かを問うような、黙考を誘う空間です。
復興から繁栄へ、トプコン拡大期のモデュロール建築「上野の国立西洋美術館」
3号館から6号館は、1980年(昭和55年)から1984年(昭和59年)にかけて、トプコンの業績が大きく伸びた時期に次々と建設されました。とはいえ、それ以前の1号館と2号館は戦前の建物。戦争が終わり軍需もなくなった後は、新しい社屋を建築する余裕などない、厳しい時代が長く続いたのです。2号館の完成から次の3号館の建築までに40年近い歳月を要したことからも、その厳しさを窺い知ることができます。
この時期に完成した社屋の中では、モデュロール建築の6号館が出色でしょう。6号館は事務系の棟として設計され、工場を主とした他の建物とは一線を画しています。特徴的なのは、少し低めの天井と大きな窓。天井を低く設定すると照明の位置がデスクワークの人に近くなり、大きな窓からの採光も天井で反射するため、室内がとても明るくなります。また、1980年代は日本でOA化(オフィスオートメーション)が盛んに提唱された時代。この新社屋には、空調などの配管や電気系の配線を壁や天井の奥に隠すダクトが設計当初から備えられ、新時代のオフィスとして好適な環境が実現しました。
モデュロール建築は、フランスの建築家 ル・コルビュジエ(1887〜1965)が提唱したモデュロールという建築理念が基調になっています。それまでのヨーロッパの建築物は、荘厳で美しいけれど、やたらと天井が高くて内部は暗く寒いものでした。これを、もっと人間の寸法、尺度に合ったものにしようと考えられたのがモデュロールです。コルビュジエ設計の東京・上野の国立西洋美術館には、その理念が明確に反映されています。
モデュロール建築を日本に広めたのは、国立代々木体育館や広島・平和記念資料館など、戦後復興期の公共建築を数多く手がけた建築家 丹下健三(1913〜2005)と言われています。彼が丹下モデュロールという日本独自の建築寸法基準を体系化すると、多くの建築家が1960〜1980年代の事務所建築に採用しました。
成長とは、変わっていくこと。時代はポストモダンへ
続く1980年代後半から1990年代初め、日本はバブル景気に踊りました。8号館や10号館は、まさにその時代の建物です。建築の世界ではル・コルビュジエや丹下健三の推奨するモダニズム建築が長く支持を集めてきましたが、戦後の豊かさが絶頂を極めたこの頃、シンプルなだけではない個性的なものを求めるポストモダンの流れが生まれました。
トプコンの8号館や10号館は、外観の一部に装飾的な階段状の造形を取り入れるなど、ポストモダンな妙味を効かせた仕上がり。インテリアにもこだわり、間接照明や素材感のある壁紙を採用するなど、効率や経済性だけでなく建物がひとに与える影響まで、より丁寧に考えた社屋となっています。
研究・設計部門のエンジニアリングセンターとして完成した10号館は、6号館に比べ天井が少し高くなりました。半世紀の時が過ぎて日本人の平均身長が伸び、職場環境の多様性も進む現代、丹下モデュロールのその先の建築寸法基準が《新しいものさし》として建築を変えつつあるのです。

時代の流れは止まることなく、新しい良いものは次々と変わっていきます。多種多様な社屋たちは、変化や変更を恐れず、常に新しい良いものに親しみ、発想と行動の土壌を豊潤に富ませておくことの重要さを静かに伝えているようにも見えます。成長とは、変化なのです。
なにげない日常と感性の質を高める、《見えない資産》
トプコンには、デザインを大切にする企業文化があります。目に見えるカタチだけでなく、目に見えない体験や、それによって引き起こされる気持ちの質を高めることもデザインの一部と考え、それをエクスペリエンスデザインと呼んでいます。
見えない美しさや心地よさに敏であるには、日頃から自分の環境にあるさまざまなモノや造形や意匠の放つ空気を愉しみ、さまざまな体感や感情を豊かに機能させ、大切に味わうことが重要だと考えます。ひとは、自分が意識している以上に、環境の影響を受けているからです。
転勤や定年などで本社を去った社員の多くは、「あの社屋が恋しい」「思えばあの頃は、なんと豊かな空間で働けていたのだろう」と語ります。社屋たちが醸す、歴史の余韻。有形無形の豊かさ。工場建屋のトイレにアールデコ様式の丸窓をあしらう、先達の粋で温かい遊び心。それを大切に維持管理して使い後進へ継承してきた、先輩社員たちの思い。それらはトプコンのエクスペリエンスデザインの根源であり、大切な《見えない資産》なのです。