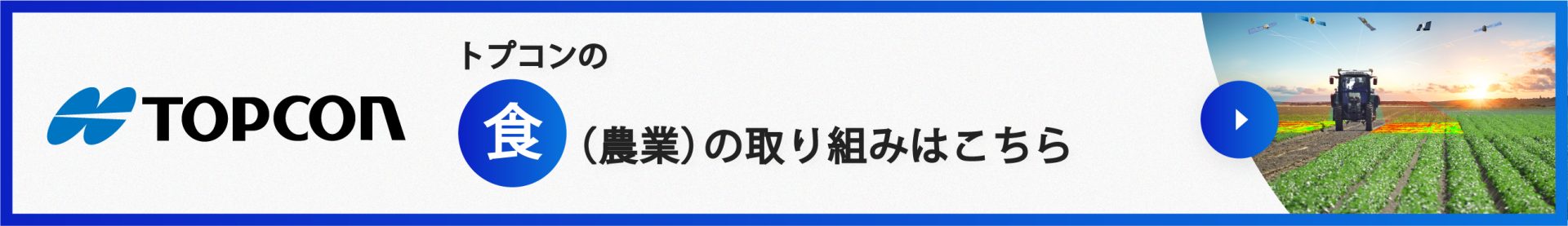目次
「旅=観光」だけの時代は終わったといわれています。趣味嗜好が多様化する現代では、「体験」「交流」「学び」「支援」等の多様なスタイルで旅を楽しむ人が増えています。旅の多様化の流れのなかで、テーマとして注目されているのが「農村体験」であり、国も力を入れて取り組んでいる“ニューツーリズム”、ヨーロッパ生まれの「アグリツーリズム」です。日本におけるアグリツーリズムの発展は、農村地域の所得向上と活性化、ひいては持続可能な農村の実現につながると期待されています。
ヨーロッパでは約70年の歴史を誇るスタイル
アグリツーリズムとは、「アグリカルチャー(農業)」と「ツーリズム(旅行)」を組み合わせた造語です。農村の豊かな地域資源を活用することを目的に、農家が旅行者を迎え入れ、農に関係する体験を通して農業や地域の魅力を知ってもらう旅の形です。起源は、第二次世界大戦後のバカンス大国フランス。今では、イタリア、ドイツ、オーストリア等、ヨーロッパ各地で人気となり、都心に暮らす人たちが長期休暇を農村で過ごす「余暇活動」として根づいています。
定義は、それぞれの国や支援組織によってさまざまですが、フランスの場合は、農村での宿泊(民宿、貸別荘、キャンプ等)、食事、レジャー(教育農場、スポーツ、レクリエーション、農場見学等)を含む全ての活動がアグリツーリズムに関わるとされています。特徴としては、さまざまな支援をする組織が古くから存在すること。2017年からは、既存の組織と、Airbnb、そして農業に特化したクラウドファンディングの会社がパートナーシップを結び、サポート力を強めるに至っています。
アグリツーリズムが一大産業として成り立っているのは、旅行者の7割が農村に宿泊するイタリアです。他国に比べて後発ながら、農村地域の過疎化や地域経済の衰退という課題を解決するため、「新しい世界を拓く」という理念のもと、定義や支援を明確にしたアグリツーリズム法を1985年に制定しました。2006年には法改正をすることで一層の発展を遂げ、アグリツーリズムが農家の収入を補い、地域の活性化や発展に大いに役立っています。
現在のイタリアでいう「アグリツーリズム」は元々の形態を指す言葉ではなく、「農家が部屋と食事を提供する宿泊施設(農家民宿)」を意味するようになり、その数は、全国で2万件以上。山岳、丘陵、平地のどこであっても、ワイナリー、オリーブ農園等々、イタリア語でいう「アグリツーリズモ」を楽しめます。運営の基準は州法で規定されており、それゆえ地域ごとに個性があり、質も高く、利用者が安心して宿泊できます。これがイタリアの特徴であり、全国へ広がったポイントといわれています。

「農泊」の一つのスタイルとして国も大いに期待
日本では、1994年に制定された「農山漁村余暇法」が最初の一歩。当初は「グリーンツーリズム(=農村での滞在型の余暇活動)」として取り組み、2018年には、農林水産省が「農山漁村滞在型旅行」を短縮させた名称「農泊」を商標出願し、持続可能な500の農泊地域の創出を目標に推進してきました。
農泊とは、「農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む農山漁村の人々との交流を楽しみ、農家民宿や古民家等を活用した宿泊施設に滞在して、観光客にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行」と国は定めています。主な目的は、農山漁村の所得向上と活性化の実現です。
農泊は、農林水産省だけではなく、観光庁や内閣府の政策にも組み込まれました。その結果、2023年度までに計656もの農泊地域を創出し、目標は達成。2023年には、農泊推進は成長期へ移行したと確言しました。そこで、政府が閣議決定した「観光立国推進基本計画」内には、さらなる成長を目指すにあたり、対象の変更を明示。これまで主な対象だった小中高校生の体験学習では先行きが見通せなくなってきたことから、国内外からの個人旅行者に希望を託し、今後支援すべき旅のスタイルとして「アグリツーリズム」を挙げているのです。

企業も取り組むアグリツーリズムの新たな動き
アグリツーリズムとしての成功モデルは日本にも多くありますが、やはり個人旅行者を増やさなければ頭打ちは否めないとのこと。そんな中で、アグリツーリズムを独自路線で展開しはじめたのが、2019年開業の「星野リゾート リゾナーレ那須」。「地域の魅力×リゾート滞在」の「アグリツーリズモリゾート」という旅のスタイルを打ち出しました。滞在の軸となるのは、那須の生産活動に触れる体験。ホテル敷地内に、田んぼ、畑、温室を設け、農作物を育てることができるのです。農業体験といっても、作物を無駄にしない農家の暮らしをヒントにしたワークショップ、地域の自然環境を活かしたアクティビティ等も用意されています。
「アグリツーリズム」に「仕事」を掛け合わせたスタイルを提案する旅行会社や人材派遣会社等もあります。JTBは、2021年にJA全農と連携協定を結び「JTBアグリワーケーション®」事業をスタートさせました。「旅行も仕事も農業も楽しもう!」をコンセプトに、農業支援を仕事として捉える新たな旅の形です。例えば、山形県の農業ツアーでは、さくらんぼ生産者の収穫や選別といった仕事を支援します。ツアー参加者はJTBと雇用契約(期間限定のアルバイト契約)を結び、農作業に従事。その対価として賃金が支払われる仕組みです。
どちらも個人が農業に触れる手始めとして、ハードルの低い内容といえます。現在、旅行の傾向は、消費傾向と同じく、モノ消費からコト消費、トキ消費へと移行しているといわれています。コト消費とは、「体験」「交流」「学び」「支援」等。「トキ消費」では、唯一無二の体験を誰と一緒に楽しむか、さらには、体験そのものに貢献できたという実感が伴うことも重要です。これらを満たすアグリツーリズムを生み出すことが企業だけではなく、農村地域にとっても課題となっています。

日本型アグリツーリズムの実現のために必要なこと
株式会社百戦錬磨、日本ファームステイ協会の「農泊手引き」によると、成果を生むためには、自分の住む農村の現状認識から始め、課題解決のためのビジョンや目標の設定、ビジョンに沿ったターゲットの絞り込み、ターゲットを意識した地域資源の磨き上げ、具体的な戦術設定(活動計画・収支計画等)の準備を進めていくことの必要性とノウハウを紹介しています。ヨーロッパのように一つの産業として成長させていくには、中間支援組織の存在や地域一丸となること、人材育成等の重要性も語られています。
同協会は、インターネット上だけで取引を行う旅行会社によるオンライン予約サイトの導入から運用までの完全サポートもスタートさせました。さまざまな支援が揃いつつある中、農村地域の取り組みもさらに広がっていくでしょう。田園回帰が高まる今、まずは農村地域への旅を増やし、唯一無二の体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。一人一人の行動は小さくとも、皆でアグリツーリズムを盛り上げれば、日本の農村や農業の課題解決へとつながっていくことでしょう。
トプコンは農業の課題解決に貢献していく企業として、世界で農業に取り組むすべての人を応援しています。
〈参考情報〉
観光庁「観光立国推進基本計画」
農林水産省「農泊の推進について」
株式会社百戦錬磨、日本ファームステイ協会「農泊手引き」
株式会社JTBプレスリリース「旅行も仕事も農業も楽しむ!「JTBアグリワーケーション🄬」ツアーを発売」