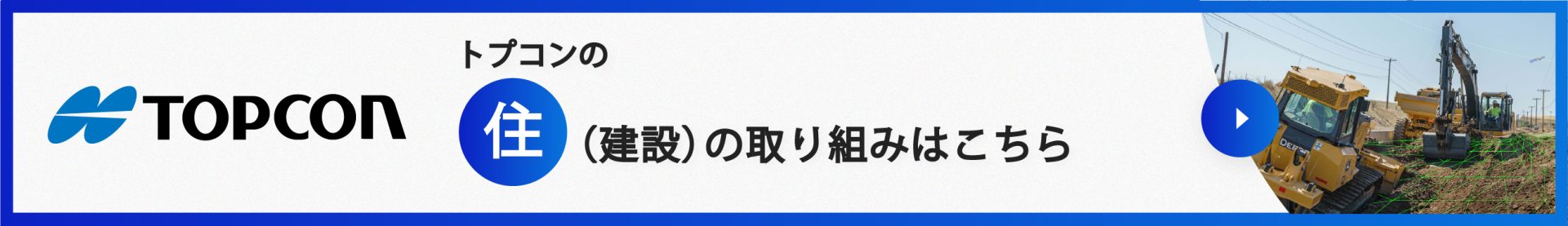目次
青森県と北海道を結ぶ青函トンネルは、全長53.85km(うち海底部分は23.30km)にも及び、世界最長の海底トンネルとして知られています。2010年にスイスの鉄道山岳トンネル「ゴッタルドベーストンネル」が開通するまでは、トンネルとしても世界最長でした。
青森県と北海道を結ぶトンネルの構想は戦前からありましたが、それが現実味を帯びたのは、1954年に台風15号による海難事故がきっかけでした。函館と青森間を航行していた青函連絡船「洞爺丸」が沈没し、死者・行方不明者1,100名以上を出す大惨事となり、安全な列車での往来を求める声が高まったのです。入念な地質調査を経て1964年に本格的に建設が着工、1988年に正式に津軽海峡線が開業しました。24年間に及んだ青函トンネルの工事は、日本にとって初めての試みばかりで、測量技術者たちにとっても大きなチャレンジでした。世界的注目を浴びた工事の変遷と測量技術に迫ります。

青函トンネルはナウマン象が行き来した道につくられた
本州と北海道を陸で結ぶ構想は、日本にとって大きな夢でした。1942年に関門海峡トンネルを開通して自信を得た日本は、1946年頃から津軽海峡の海底トンネル建設の事前調査を開始しました。本州の最北端は、青森県の東側に突起している下北半島の大間崎です。当初は青函トンネルも、下北半島から北海道亀田半島最南端の汐首岬に通す案が挙がっていました。しかし、東側を通るこのルートは氷河時代も海で、水深が270メートルと深いことが分かりました。水深が深いほど、水圧は高くなります。また、鉄道は急勾配を走ることができないため、約270メートルに潜っていくまでの距離を長く取らなければなりません。

さらに、昭和新山や有珠岳、恐山や八甲田山などの那須火山帯がルート上に存在することも懸念材料となりました。そこで、水深が約140メートルと浅い津軽半島の竜飛岬から北上するルートが採用されました。このルートは、氷河時代に氷が張って陸でつながっていたとされ、その後の氷解期に海面が上昇し、海流によって津軽海峡ができたと考えられています。氷河時代には、ナウマン象(マンモス象)などが行き来していた可能性があり、青函トンネルはその古代のルートを再現しているともいえます。
約10年間にも及ぶ津軽海峡の海底地質調査を開始
青函トンネル建設に先立ち、約10年間に及ぶ海上からの地質調査が行われました。海底の地形や地質学上の自然条件を詳細に調べることで、当時の技術でトンネル建設が可能かを判断するためです。最初の調査は、岩石採取作業から始まりました。チリトリのような形状の鉄製バケット(ドレッジャー)をワイヤーロープで船に装着して沈め、海底を引っ掻きながら岩石を攫って集めました。船を少しだけ進ませてはバケットを引き上げ、回収したわずかな岩石を調べるという地道な作業です。バケットが岩と岩の間に引っかかると、船が引っ張られて沈没するおそれがあるため、ワイヤーを切断できる大きなマサカリや、巡視船が来た時に回収してもらえるようブイ代わりにするドラム缶も用意されていました。
船には測量室が設置され、位置関係は六分儀を使って、予め海岸の目立つ岩に白い石灰を塗った標識との角度を調べて測定する三点両角法を用いました。さらに、音波を海底下の地層にまで発信して反射波を分析することで地質構造を明らかにし、小型潜水艦による目視調査も行い、詳細な地質図を作成しました。そして、トンネル工事は可能であるという結論に至ったのです。
両側から掘り進めたトンネルが貫通するまで
地質調査によりトンネル工事は可能であるとの結論が出されましたが、当時のトンネル掘削技術はまだ発展途上であり、実際に掘ってみなければ技術的に可能なのかを判断するのは難しいものがありました。そのため、調査坑の掘削が切望されていましたが、なかなか実現に至らず、1963年にようやく掘削のゴーサインが出されたのです。調査坑は、本州側と北海道側の両端から斜めに海底へと向かい、海峡の中央部に水平坑(後の先進導坑)を掘ることになりました。

この初期の調査坑を通じて得られた技術的な知見を基に、1971年9月には、本坑の掘削がいよいよ開始。本坑も、調査坑と同様に、両側から同時に進められました。そして、最終的に2つの坑道が交わる海峡の中央点では、水平位置も高さも10cm程度の誤差で収める必要がありました。しかし、北海道と本州は隔離されていたため、二等・三等三角点が関連しておらず誤差は最大30cmであると予想されていたのです。
そのような状況下で精密な作業を達成するため、ジオジメータ(光波測距儀)やセオドライト(経緯儀)を据え、海を挟んで長距離間の距離や高低差を求める渡海三角測量と渡海水準測量が実施されました。これらの測量機は光を用いて測定しますが、トンネル内には排水管やエアー管、換気ファンなどが近接しており、これらの設備から生じる温度差による光の屈折(温度勾配)が現れ、大きな誤差が生じることが発覚。この誤差を考慮するため、何度も試行錯誤を繰り返しながら測量が進められました。結果、世界最長となる距離を結ぶ坑道にもかかわらず、誤差はcm単位の誤差に収まり、見事に貫通させることができたのです。

開業から30年超、現役の青函トンネルに欠かせないモニタリング
こうして1985年に本坑が開通、1988年に津軽海峡線として正式に開業した青函トンネル。開業から30年を超えた今も、本州と北海道をつなぐ海の道として活躍を続けています。国内には、青函トンネルのように完成から数十年を超えるトンネルや橋が数多く存在し、2030年には約55%の道路橋、約36%のトンネルが建設後50年を迎えるとされています。人々の生活を安全に支えるために、こうしたインフラの維持に欠かせないのがモニタリング。トプコンは構造物の精密なモニタリングができるMS/NETシリーズの高精度測定機器を提供しています。本シリーズには、超高精度な測距・測角システムが搭載されており、オンラインでの遠隔操作が可能。指定した範囲のターゲットを自動でモニタリングし、構造物のわずかな動きやズレを見逃しません。インフラ設備や工事現場での早期異常発見と災害防止にも役立ち、安全なトンネル工事やメンテナンスの運用をサポートします。

人々の暮らしを支えるトンネルや橋。トプコンは、「はかる」技術で人々の安全な暮らしを支えていきます。
【参考文献】
・交通新聞社「青函トンネル物語」
・中央新書「青函トンネルから英仏海峡トンネルへ」
・講談社「ドキュメントノベル 青函トンネル」