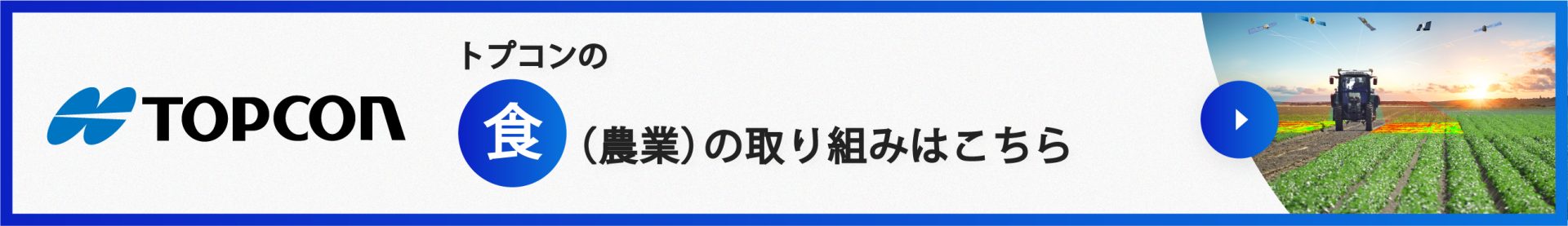目次
近年、国内生産が拡大している野菜といえば、パプリカ。以前は韓国を中心とした輸入品が圧倒的なシェアを誇っていましたが、近年は消費者ニーズの高まりから、国内産を支持する声も増えたことで、国内でも栽培に着手する農家が増えています。その影響を受け、各種苗メーカーもさまざまな品種を開発しています。今後、国産品としての伸びしろが期待できるパプリカ栽培の現状と、そこにスマート農業が貢献できる可能性についてご紹介します。
パプリカとはどんな野菜?
赤や黄色など、カラフルな色合いからサラダや炒め物などに使われるパプリカ。パプリカはピーマンやトウガラシと同じ「ナス科トウガラシ属」に分類される野菜です。日本では果実色の特徴からカラーピーマンと呼ばれているものもありますが、実はパプリカはカラーピーマンの一種。100g以上の大型で肉厚のカラーピーマンのことを指します。
緑色のピーマンは未熟状態で収穫されますが、パプリカは完熟果実。そのため、ピーマンのような青臭さや苦味はなく、甘くてフルーティな食感が特徴です。また、成熟してから収穫するため、ピーマンよりも栄養価は高く、ビタミンCはピーマンの約2倍、カロテンは約7倍という差が。また、ビタミンCは熱に弱いとされていますが、パプリカは厚い果肉に守られているので、加熱しても栄養素が壊れにくいともいわれています。
今ではスーパーや青果店で普通に目にするパプリカですが、1990年代にオランダからの輸入が開始されるまでは国内ではほとんど知られていなかったとか。一方、アメリカやヨーロッパでは緑色のピーマン以上にメジャーな食材でもありました。

海外と国内におけるパプリカの生産・消費の現状
現在、日本で流通しているパプリカのシェアは、およそ9割が輸入品。その多くを韓国産が占めています。韓国におけるパプリカ生産は、大韓航空の機内食用として1994年に済州島で栽培したのが本格的な生産の始まりとされています。以降、生産増加の一途をたどり、2004年は20,551トンだった栽培量も2006年は8,000トン増加し、28,148トンに。その後も右肩上がりに成長を続け、2021年には80,000トン以上にまで増加しています。増加の理由は、日本を中心に海外需要が高まっていること。また、韓国国内でも消費量が伸びていることが成長の要因です。
その数字が指すように、日本ではパプリカの需要は急増しています。2000年には年間輸入量が10,250トンでしたが、2020年では30,143トンまで上昇。そのうち韓国産が82%を占めています。

種苗メーカーも続々開発。国内パプリカの注目の品種とは?
韓国産がシェアの大半を占める中、日本国内のパプリカ生産量も近年は増加しています。2022年の作付面積は81ヘクタールと、10年前に比べて1割増、さらに収穫量は7,380トンと8割増になりました。日本ではパプリカの本格的な栽培が始まったのが20年ほど前からといわれている比較的新しい野菜。しかし、消費者からは「国産だから安心」「新鮮でおいしい」という理由から高く支持され、国産パプリカの認知度は広がっています。事実、輸入品は消費地に届くまでに日数がかかるため、熟す前に収穫される場合が多く、その一方で国内産はギリギリまで熟してから収穫するため甘みも強くなり、また鮮度も当然ながら良いため、高い評価につながっていると考えられます。その点からも国産のニーズは今後さらに高まるといえるでしょう。
現在、作付面積の上位県は宮城県、茨城県、長野県、山形県、北海道など。その他の地域でもパプリカの将来性を見込んでパプリカ栽培に乗り出す生産者が増えています。また、価格面で見ても、韓国からの輸入品が1kg350〜400円に対し、日本産は1kg600〜700円で取引されるなど、高価格をキープ。消費者からのニーズに加え、価格の面でも高く評価されている点が生産拡大を後押ししています。
さらに、パプリカの人気もあり、国内では通常のパプリカより小さいフルーツパプリカにも注目が集まっています。各種苗メーカーでも多様な品種が登場している中、注目したい品種が「ぱぷ丸」「セニョリータ」など。「ぱぷ丸」は高温にも強いなど、栽培のしやすさが注目される理由となっています。また、「セニョリータ」は色づきが早く、多収な品種。どちらの品種も一般的なパプリカと比べてミニサイズのため、調理の際に使い切りやすいことが特長です。そして糖度が高く、甘みが強いため生食に適していることも人気の理由です。

パプリカで新規就農を目指すなら。スマート農業で高効率の農業を実現
これまで日本のパプリカ市場は輸入品に支えられてきたため、国内産は後から市場に参入する格好となっています。しかし、その分、国産に期待する声も大きく、新たに導入したい作物であることは間違いないと思われます。また、生産する側にとって、カラフルな作物を育てることは、成長過程で色が変わる様子を見られるといったシンプルな楽しさがあり、それが生産拡大の一因となっているようです。
パプリカをはじめ、新しい農作物の栽培に取り組む機会にぜひ導入を検討したいのがスマート農業です。実際に宮城県ではパプリカ栽培の生産現場にスマート農業を取り入れることで、着実に成果を出しています。スマート農業によって農作業のデジタル化を加速すれば生産効率が向上し、持続可能な農業を実現できます。
トプコンでは、長年培ってきた光学技術、GNSS技術、また、各種センサーやネットワーク技術を駆使し、農機の自動運転システムやレーザー式生育センサーによる穀物の生育状況の見える化により、農作業の自動化を実現しています。農業初心者でも熟練者並みの効率のいい作業が可能になるなど、生産性や品質の向上に貢献しています。
トプコンはスマート農業へチャレンジする農家の皆さんを応援しています
〈参考資料〉
韓国のパプリカの生産、流通および日本への輸出動向―独立行政法人農畜産業振興機構
韓国のパプリカの生産、流通および日本への輸出動向―独立行政法人農畜産業振興機構 (PDF版)
パプリカ生産における国内・外の生産・流通の変化―独立行政法人農畜産業振興機構