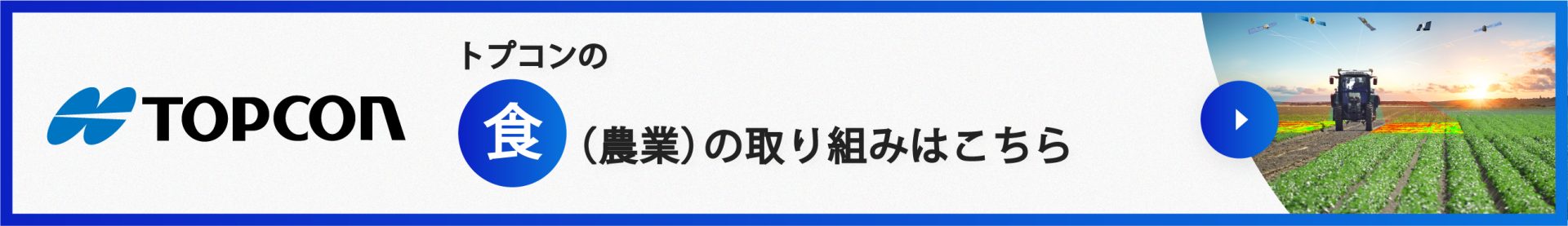目次
最近、話題になっている「ヤシ殻培土(ココピート)」は、ココヤシの果実の殻などでつくられた有機物100%の栽培用の「培土」のことです。トマトやイチゴなどの施設栽培などで利用されており、環境への配慮やごみ削減などを実現できることから注目を集めています。そのメリットは環境面だけでなく、ランニングコストの減少や肥料の減少など、コスト削減にも繋がる点も大きな魅力に。そんな高評価を得るヤシ殻培土のメリットやデメリット、使い方などをご紹介するとともに、次世代型の農業資材やスマート農業を取り入れることで実現できる次代の農業を探ります。
次世代の培土として期待される「ヤシ殻培土」って何?
「ヤシ殻培土(ココピート)」とは、その名の通り、椰子(ココヤシ)を原料とした「培土」。主にインドやスリランカ、フィリピンなどで栽培されている椰子の内皮にある繊維などを使った土壌改良材です。
これまで、土壌改良材としてはロックウール(人造鉱物繊維)やピートモス(苔などの植物が腐食物質となって蓄積した泥炭を乾燥させたもの)が多く使われていました。しかし、ロックウールは鉱物のため、捨てる際は産業廃棄物として処理する必要があります。また、ピートモスは採掘時の環境への影響が懸念されるなど、従来の土壌改良材は地球環境に与える影響が問題視されつつありました。そこで、これらの課題を解決する次世代の土壌改良材として、ヤシガラ培土に期待が寄せられています。
イチゴやトマト、きゅうり、パプリカ、ブルーベリーなどを育てる際、土を使用せず肥料を水に溶かした培養液で育てる栽培法を養液栽培といいますが、ヤシ殻培土は養液栽培の作物が根を張る培地に適しているといわれています。また養液栽培だけでなく、優れた保水力や保肥力、通気性などを活かし、栽培する作物や用途に合わせた様々な商品が販売されています。例えば、育苗用のポット型や、根を他の作物から隔離して栽培できるビニールバッグ入りのもの、レタスなど各種野菜の栽培用の培養土に配合されたものなどがあり、様々な作物の栽培で活用できるようになってきました。

農作業の省力化や環境への配慮など、メリットの多さが特徴
ヤシ殻培土のメリットは数多くあります。原料となる椰子の殻は小さな穴が無数に空いた多孔性のため、空気や水分を蓄えることができるのが大きな特長の一つ。作物に必要な水分を保持しながら、多孔質構造のため余分な水分はしっかりと排出する。そんな水持ちと水捌けの両方を兼ね備えた培土であることから、作物にとって最適な土壌状態をキープすることが可能です。また、ヤシ殻培土のpH(土壌酸度)は5.5〜6.5程度。よく比較されるピートモスのpHは4.0前後と酸性のため、アルカリ性の資材で酸度を調整する必要がありますが、ヤシ殻培土の場合は多くの作物が好む弱酸性〜中性の範囲なので、pHを調整する手間が省ける点も高く評価されています。さらに、その軽さも大きな魅力。通常の培養土に比べてその重さは半分以下のため、女性や高齢者でも扱いやすく、作業労力を軽減でき、作業効率アップにもつながります。

しかも、ヤシ殻培土は通常は捨てられてしまう椰子の殻を活用した地球環境にやさしい有機培土。天然素材のため、培地として使用した後は堆肥として圃場にまけば、廃棄コストはもちろん0円です。今の時代に適したサステナブルな培土であることも注目される理由になっています。さらに環境への配慮やごみ削減などを実現できるだけでなく、ヤシ殻培土は比較的費用が安価で、数年に1回の取り替えで済むなど、導入コストやランニングコストを抑えられるところも生産者にとっては大いに助かるところ。保肥性も高いため、結果として肥料の使用量も減少するなど、諸費用の点でも大きな魅力があります。

逆にデメリットは? 品質のバラツキが問題に
多くのメリットがあるヤシ殻培土ですが、天然素材ゆえにデメリットがないわけではありません。その一つが、窒素やリン、カリウムといった肥料を含むことから作物の味などに多少の影響があること。しかし、これは硝酸カルシウムを培地に置換させて初期栽培を安定させるバッファリング処理を使用前に行えば解決します。また、EC(含有塩分濃度の指標)が高いものだと作物の根がやられてしまうものもあるため、商材によっては洗浄が必要なものも。どうしても有機物のため品質にバラつきがあるので、使用にあたっては製造工程や成分内容、含有塩分などの点を踏まえて選ぶことが大切です。
一方で、農業試験場ではヤシ殻培土を使った生育研究が続々と発表され、生産者の間でも利用が広まっています。今後、ヤシ殻のような新たな有機培土の活用はますます広がっていくと考えられます。

技術や資材、新しい作物品種など、農業を取り巻く環境は年々進化し、選択肢も増えています。将来に継続できるサステナブルな農業を続けるためにも、今の時代に適した農業のカタチを取り入れることで、食と農の可能性がさらに広がるはずです。
トプコンは「農業の工場化」をコンセプトにDXソリューションを提供。スマート農業へチャレンジする農家の皆さんを応援しています。
〈参考文献〉
徳島県立農業試験場〜ヤシガラ培地を用いたトマトの循環式養液栽培
福岡県農林業総合試験場〜即成ナスの溶液栽培用培地としての「細粒礫」および「ヤシガラ」の適応性
千葉県「農業改良普及情報ネットワーク フィールドノート令和2年 ヤシ殻培地耕によるトマトの長期どり栽培」
農研機構 東北農業試験研究協議会「東北農業研究第56号」〜期待される新野菜の固形培地耕栽培における生育特性
熊本県農林水産部「簡易隔離床を利用した促成トマトの高品質栽培における培地運用のための土壌改良資材と追加量」
公益財団法人国際緑化推進センター〜3.3ヤシ殻(ココピート)
脱天然資源依存の英国園芸:ピート削減に向けた王認園芸協会(RHS)の取り組みを中心に