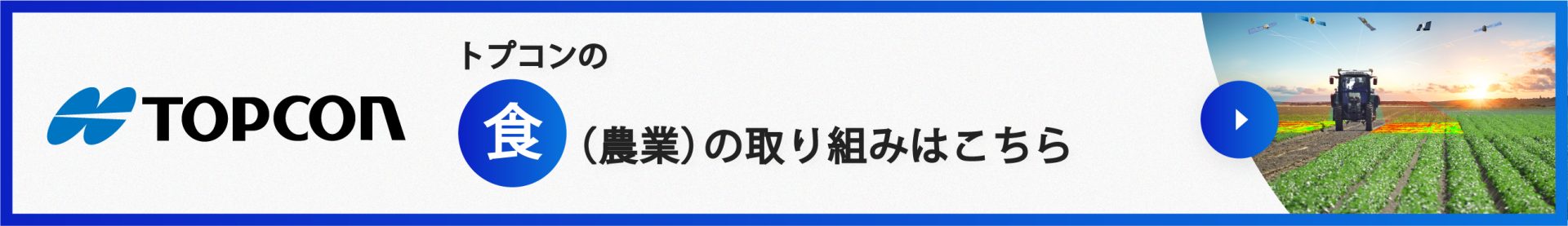目次
作物を育てる際の厄介者といえば、雑草です。雑草が土の養分を奪ったり、日当たりを悪くして植物の成長を妨げたりと、農家にとっての雑草対策は悩ましい問題です。現代では様々な除草方法があり、それぞれのメリット・デメリットを知った上で今後の対策に活かしたいところ。その一方で、雑草を農業に利用する活用方法も近年は生まれています。そこで、雑草によるトラブルや除草で気をつけたいポイント、そして、新たな雑草の活用方法など、雑草とうまく付き合う方法についてご紹介します。
雑草は農地・作物にとって悪なのか。農家を悩ます雑草問題
農作業をする上で手を焼くのが雑草対策。特に夏の時期は定期的に草刈りや草取りをしてもすぐに成長し、まさに雑草との戦いはイタチごっこ状態です。農家の高齢化や人手不足も深刻になる中、防草・除草作業は重要ながらも、時間も労力も取られる作業になっています。
しかし、もし雑草をそのまま放置したならどうなるのでしょうか。雑草を放置すると、雑草が土の養分や水分を奪ってしまい、作物に必要な栄養分や水分が行き渡らなくなりますし、雑草が農作物以上の高さに育つと、日光を遮ってしまい、作物の成長の妨げになることが挙げられます。雑草についた病原菌により農作物が病気になったり、枯れたりすることも当然ありえます。また、穀物のような収穫物に雑草の種が混じれば、等級が下がって値段も下がるというデメリットがあります。そのため、雑草は繁殖する前にできるだけ早いタイミングで取り除くのが重要です。

畑の雑草を処理する方法とは?
では、雑草をどのように処理するのが有効なのでしょうか。一つは除草剤を使うこと。ただし注意したい点は、除草剤は種類により農作物を介して人体に影響が出たり、土壌汚染など環境汚染につながったりするものもあるため、安全性が確認されているものを選ぶことは必須です。その上で除草剤を撒くタイミングにも注意が必要です。適切でない時期に行っても効果が出ないため、正しい撒き方や時期は前もって調べておくことが肝心です。
除草剤の種類のうち、撒いた成分が土壌に移行して、雑草の根から吸収されることで雑草の生長を阻害する「土壌処理型」は、春先の2~3月ごろに利用するのが一番よいとされています。また、秋に生えてくるものには9〜10月頃に撒いておくと、翌春の雑草を減らせるという利点も。そう考えると、春秋の2回に撒くのが効果的だといえます。
一方、既に生えている雑草の葉を枯らす「茎葉処理型」の除草剤を使うのは、雑草が生い茂り始める4〜10月頃が効果的。雨の日や風が強い日に撒くと流れてしまうため、天気がいい、風のない日を選ぶのがおすすめです。
そして、機械除草による草刈りの場合は、雑草が大きくなるのは初夏から秋にかけてのため、まずは雑草の花期が集中する時期までに行うようにします。その他、黒マルチや除草シートを使う方法では、上からこれらを雑草の上に被せると日光が遮られ、光合成ができなくなった雑草はやがて枯れていきます。この方法は雑草の発生を予防する効果があります。

さまざまな除草方法のメリット・デメリット
除草剤、草刈り、防草シートなど、雑草対策はさまざまありますが、優先すべきなのが、土壌をいかに最適にするかということ。つまり、作物を育てる土壌に負荷がかからない方法を選ぶことが大切です。例えば、除草剤は効率よく雑草を枯らすことができますが、土壌のpHが低下して酸性化が進み、土を肥やす微生物が死滅するデメリットが考えられます。
また、機械による除草では、雑草が再び生えてくるのを防ぐために手作業による草抜きも同時に行うことがあります。このとき、雑草を取り除くことで土が硬くなるというデメリットも。雑草を根ごと引き抜くことで、根が張っていた部分の土が締まってしまうという現象です。さらに、硬い土でも繁殖する根の張りの強い雑草が生えやすくなることもあります。
他にも黒マルチや除草シートも雑草除去に効果がありますが、効果が出るまで時間がかかるといわれています。雑草の量も、減りはしますが完全に防げるわけではありません。

雑草を有効活用し、環境にやさしい取り組みにも目を向けてみる
農家の悩みの種でもある雑草対策をどうすればいいのか。農家に伝わる諺(ことわざ)に、「上農は草を見ずして草を取り、中農は草を見てから草を刈り、下農は草を見て草を取らず」という言葉があります。その言葉が示すように、雑草が生える時期を知り、栄養を取られないうちに草を取ることが何より大事だということ。そうするためには、草が出るか出ないかのうちに草を削り取ることがベストですが、草が生える前に何度も除草する必要があり、それができないからこそ多くの農家が悩んでいるところです。
その一方で、近年は雑草を活かした活用法も検討されています。例えば、刈り取った雑草を利用して地表を覆い、ビニールマルチに替わる「雑草マルチ」として使用すること。この雑草マルチは雑草が土の温度を調整したり、乾燥を防いだりする役目をしてくれ、使用後はその雑草が枯れて、いずれは土壌づくりの肥料になるというものです。また、刈り取った雑草を「雑草堆肥」として利用する生産者も増えてきました。雑草に米糠を混ぜ合わせて発酵させると、栄養バランスのいい雑草堆肥が出来上がります。雑草堆肥は化学肥料とは異なり、植物性資材でできているため環境への負荷を減らせます。
これまで無駄だと思われていた雑草も、目先を変えると新たな活用方法が生まれます。しかも、今まで捨てていた雑草を資源に変えるという循環型農法は、今の時代にふさわしいサステナブルな取り組みでもあります。雑草をすべて害悪とは考えず、雑草の活用法にも目を向けるなどしてうまく付き合っていくことも今後の農業には大切になってくるのではないでしょうか。
トプコンはスマート農業の推進を通じて、サステナブルな農業を応援しています。
〈参考文献〉
大串龍一『病害虫・雑草防除の基礎』2000、農文協
伊藤操子『雑草学総論』1993、養賢堂