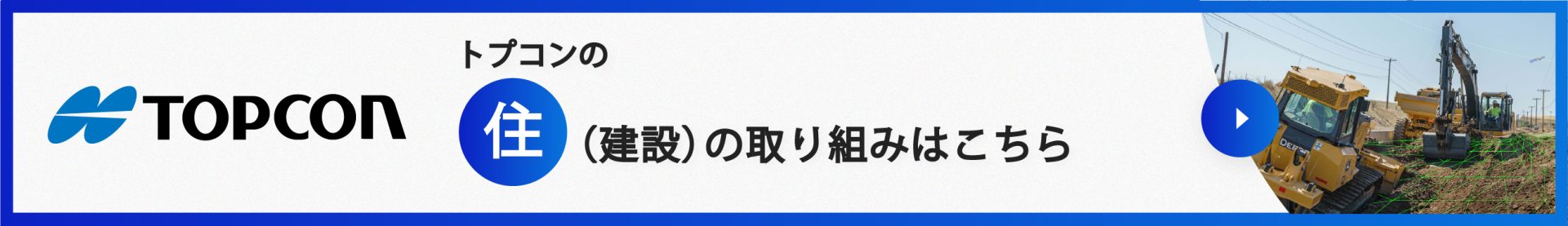目次
一般社団法人日本地下鉄協会によると、地下鉄とは「都市の地下部分に建設されたトンネルの中を走行する鉄道」を指します。日本地下鉄協会が認定している地下鉄は、札幌・仙台・東京・埼玉・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡の11都市に及び、営業路線総延長は800km以上、利用者総数は1日あたり1,765万人に達しています。なぜ、地下鉄はこのように大都市部につくられてきたのでしょうか? その歴史を紐解きながら、地下鉄車両の製造工程と、それがどのようにして地下の線路に配置されるのか、その詳細について解説します。
地下鉄の起源と日本の導入
世界で最初に地下鉄を開通させたのは、1863(文久3)年のロンドンにあるメトロポリタン鉄道でした。当時日本はまだ江戸時代で、鉄道が日本で初めて開通する10年近くも前のことです。最初は蒸気機関車による運行だったため、トンネル内に噴煙が充満し、評判は芳しくありませんでした。しかし、1890(明治23)年に電化されると、クリーンで効率的な交通手段として広く受け入れられ、都市の交通革命を牽引する存在となりました。

日本での地下鉄開業は、1917(大正6)年に早川徳次(はやかわ のりつぐ)が発起人となり、東京地下鉄道株式会社を設立したことに始まります。1914(大正3)年に「鉄道と港湾」の研究のためにロンドンに赴いた徳次は、地下鉄の利便性に感銘を受け、東京にも地下鉄をつくりたいと強く思います。当時の東京は人口200万人を超え、急速に発展する都市でありながら、交通インフラは未整備で、路面電車が導入されたばかりの混沌とした状況でした。交通渋滞や遅延が日常茶飯事だったため、地下鉄の導入はまさに都市の救済策であると考えたのです。そして、1927(昭和2)、彼の強い熱意がようやく実現し、上野から浅草までの2.2キロメートルの区間に地下鉄銀座線が開業しました。
その後、東京市が地下鉄の公営化を目指しましたが、財政上の困難から実現できませんでした。そこで、現東急グループの創始者である五島慶太のもとに設立された東京鉄道株式会社が事業を引き継ぎ、渋谷から新橋までを開業させました。そして、1941年(昭和16年)、東京の地下鉄事業は帝都高速度交通営団(現:東京メトロ)に譲渡され、公営化されました。東京に続いて地下鉄を建設した大阪では、当初から大阪市が事業主体となって計画を推進し、1933年(昭和8年)に梅田〜心斎橋間を開業させました。
自治体主導で地下鉄の開通が多い理由
その後、各都市で開通した地下鉄も自治体が主導となり、経営においても、現在、首都圏の東京メトロ(東京地下鉄)と近畿圏のOsaka Metro(大阪市高速電気軌道)以外は、各自治体の交通局が担っています。どうして、地下鉄の開通は自治体が主導となることが多いのでしょうか。理由のひとつは、地上の所有権の問題からできるだけ公道の地下に建設する必要があるためです。その関係上、地下鉄の路線には公道に合わせた急カーブが比較的多く見られます。また、地上構造物の基礎杭や他の地下の埋設物(電気、ガス、水道管など)を避けるために、急勾配も比較的多いそうです。
大都市では複数の路線が建設されていますが、後から建設される地下鉄は、既にある地下建造物を避け、空いている用地を確保するためにさらに深い地中に建設されることが多くなります。日本一深いところにある地下鉄駅は、東京・大江戸線の六本木駅で、地表から42.3メートル。7階建てのビルに相当する深さです。建設する場所が深くなれば建設費もその分高くなるため、その回収を見込んで、後からできた地下鉄ほど運賃が高くなる傾向があります。

例えば、東京メトロと都営地下鉄では、初乗り運賃はあまり変わらないものの、距離が長くなるにつれて、後に開通した都営地下鉄のほうが運賃は高くなります。地下鉄には建設費だけでなく、トンネルの維持管理にも多額の費用が必要となります。これらの費用を賄うために、地下鉄は、多くの利用客が見込める大都市で運行されているのです。

地下鉄車両の進化と現在の製造・搬入方法
現在、地下鉄の運行は延伸や相互乗り入れにより、地上を走る鉄道が地下に入ることも少なくありません。そのため、「鉄道に関する技術基準を定める省令」では、地下鉄以外の車両についても、トンネル内の乗客の安全を確保する観点から、地下鉄用旅客車両の基準が考慮されています。
例えば、トンネル内での緊急時に乗客が避難できるよう、車両の前後に貫通口を設けることが義務付けられています。また、トンネル内での火災対策として、車両には不燃性や難燃性の素材が使用されることも規定されています。
車両の製造は、まず部材の組立から始まります。次に、車体の構体組立が行われ、その後、内部の艤装(ぎそう)組立が進められます。続いて台車枠の製造と台車の組立、台車の検査を経て、最終的に台車が車体に取り付けられます。総務省の資料「鉄道車両の生産工程」によると、車両の製造期間は、既存の車両の増産の場合は10〜12ヶ月、新設計の電車(在来線)の場合は約18〜22ヶ月以上を要するとされています。
では、完成した地下鉄車両はどのようにして地下に入るのでしょうか。地下鉄線が地上とつながっている場合は地上から直接乗り入れますが、そうでない場合は地下に車両基地を備え、その近くに設けられた搬入口からクレーンで車両を下ろします。この搬入口は公園の一角などに設けられており、普段は閉鎖されているため、一般にはほとんど知られていません。また、一部の地下鉄では、車両を搬入するために専用のトンネルルートが用意されています。

地下鉄の運行や安全を支えるためには、高度な技術と正確な計測が不可欠です。トプコンの高精度な計測技術をもとにした製品やソリューションは、インフラの維持管理において重要な役割を果たしています。

トプコンのモニタリングシステムは、トンネルや橋梁など構造物の変位をリアルタイムで監視し続けることで、異常が発生した際には迅速に対応することができます。また地表面の変位をモニタリングする「ランドスクリーニング」サービスもそろえており、インフラの維持管理コストの削減に貢献します。
従来、決まった点を定期的にトータルステーションで単点計測してトンネルの内空変位をモニタリングしていたものを、トプコンのレーザースキャナーにより3D面管理をすることで、3D設計データと現況との差異をより詳細に把握することができます。カーブや合流など複雑な形状のトンネルでも正確にスキャン計測ができるトプコンのレーザースキャナーは、インフラの設計・施工・管理をサポートします。
地下鉄は、地下走行による高速性と定時運行で都市の交通渋滞の緩和に寄与します。また、二酸化炭素(CO₂)排出量が少なく環境に優しい公共交通機関であり、近年は、高齢者や外国人など誰にでも利用しやすいユニバーサルデザインも進んでいます。トプコンの技術はこのようなインフラの発展を支え、これからも進化し続けます。
(参考文献)
ミネルヴァ書房「鉄道とトンネル」
グランプリ出版「鉄道車両メカニズム図鑑」「鉄道工学ハンドブック」
交通新聞社「地下鉄誕生」
三笠書房「読めば読むほどおもしろい 鉄道の雑学」