目次
2024年8月、トプコンはフランスで遠隔診療プラットフォームの導入を行っているスタートアップ企業TESSAN社とのパートナーシップを締結したと発表しました。
フランスの遠隔診療スタートアップ企業 TESSAN, Inc.とパートナーシップを締結
TESSAN社は、フランスのQOV(Quality of Vision=視覚の質)の維持・向上に貢献するというビジョンを掲げ、遠隔診療プラットフォームの導入を行っている企業です。フランスでは高齢化と眼科疾患の増加により、眼科医のリソースがひっ迫し、眼鏡を作るだけでも数カ月待つような事態が常態化しています。より迅速で効率的なワークフローへの需要と期待が高まっている中、トプコンの診断機器とTESSAN社のプラットフォームを組み合わせることで、患者は診断や紹介を含め治療へ格段に速くアクセスできるようになることが期待されています。
「スタートアップ」という言葉は、最近耳にすることが多くなりましたが、実は以前から存在するビジネスモデルです。スマートフォンやキャッシュレス決済といった、私たちの生活を大きく変えたサービスの多くがスタートアップから生まれました。本記事では、スタートアップが注目される理由と、日本におけるスタートアップの動向について解説します。
スタートアップとは?ベンチャーとの違い
経済産業省の資料「スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する」によれば、スタートアップとは「新しい技術やビジネスモデル(イノベーション)を有し、急成長を目指す企業」とされています。「イノベーションを生み出す企業」という点では、日本では「ベンチャー」という言葉のほうが馴染み深いかもしれません。
スタートアップとベンチャーの違いは、「短期間で大きな成長を目指すかどうか」にあります。ベンチャー企業は、着実で長期的な成長を重視し、既存ビジネスから新市場を開拓する傾向があります。しかし、スタートアップは、全く新しいビジネスモデルを展開して急成長を目指す企業であり、赤字覚悟で積極的な先行投資を行う傾向があります。そのため、ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家からの出資(エクイティ)で大規模な資金を調達し、技術やビジネスモデルの実現に挑戦するケースが多い点が特徴的です。

スタートアップは若者の特権と思われがちですが、実際には40代以上の起業家が成功するケースが多いことがわかっています。ハーバード・ビジネス・レビューの調査「Research: The Average Age of a Successful Startup Founder Is 45」によると、米国における成功したスタートアップ創業者の平均年齢は45歳でした。また、日本政策金融公庫の「2023年度 起業と起業意識に関する調査」によれば、日本の起業家でも40代が最も多く占めています。これは、業界で培った経験や人脈が信頼を得やすく、資金調達や事業運営において有利になるからだと考えられます。

スタートアップが注目される理由
スタートアップという言葉が一般的に使われるようになったのは近年のことですが、振り返れば、現在の大企業の中にもかつてはスタートアップだったものが多く存在します。特に1990年代後半以降、ICT技術の発達により、大きな固定コストをかけずに起業し、短期間で急拡大を目指すビジネスモデルが次々と登場しました。その代表例がプラットフォームビジネス です。
プラットフォームビジネスとは、異なるユーザーやグループを結びつける仕組みを構築し、収益を生むビジネスモデルを指します。例えば、ECサイト(Amazon)や検索エンジン(Google)は、製品やサービスの提供者と利用者を結ぶプラットフォームの典型例です。規模が大きくなるほどネットワーク効果が生まれ、さらに成長スピードが加速する特長を持っています。
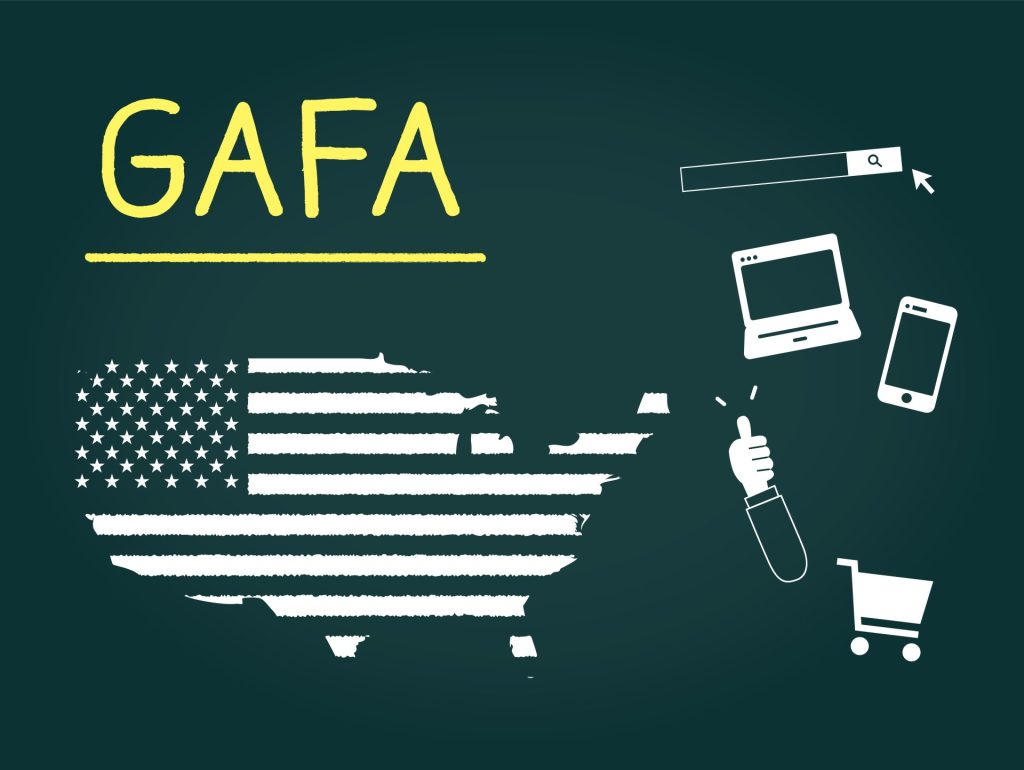
現代を代表するGoogle、Apple、Facebook(Meta)、Amazon、Microsoft(総称してGAFAM)はすべてプラットフォームビジネスを採用しており、各企業がそれぞれのプラットフォームで市場の成長を牽引しています。ダイヤモンドオンラインの分析によれば、GAFAMを除くと、日本(TOPIX)と米国(S&P500)の株式市場のパフォーマンスはほぼ同じであることが示されており、スタートアップの存在が市場成長の主要な要因であることが浮き彫りになっています。また、経済産業省の資料でも、日本のスタートアップがもたらすGDPの創出額は19.4兆円(間接効果を含む)と推計されており、スタートアップは日本の経済成長にとって極めて重要な存在であることがわかります。
さらに、スタートアップは社会課題の解決や社会貢献の場面でも注目されています。例えば、新型コロナウイルスのワクチンをいち早く開発・実用化したビオンテックやモデルナは、いずれもスタートアップ企業です。加えて、スタートアップは新しい産業を生み出すため、多様な職種や雇用の場を提供し、社会全体の経済活動の活性化にも寄与しています。
日本におけるスタートアップ動向
日本のスタートアップ企業は、数や規模の面でアメリカや中国などの主要国に後れを取っているのが現状です。2024年7月時点でユニコーン企業(企業価値が10億ドル以上の未上場企業)の数は、アメリカが666社、中国が167社に対し、日本では8社にとどまっています。この差の背景には、起業環境や資金調達に関する課題があります。たとえば、日本では起業時のリスクを避ける傾向が強く、金融機関から融資を受ける際に経営者個人が会社の連帯保証人となる「経営者保証」の慣習があることもスタートアップの成長を阻害する一因といわれています。また、スタートアップ企業の成長段階は一般的に「シード」「アーリー」「ミドル」「レイター」に分けられますが、日本では事業が軌道に乗り、売上も安定してきた「レイター」段階の企業に資金供給の多くが集中しており、「シード」や「アーリー」段階の支援が十分とはいえないことも課題の一つです。
こうした現状を踏まえ、日本政府は2022年を「スタートアップ創出元年」と位置づけ、包括的な支援策を開始しました。その中心となるのが、「スタートアップ育成5か年計画」です。この計画では、社会課題の解決や産業構造の変革を担うスタートアップを育成するため、「資金供給の強化」「人材育成」「オープンイノベーションの促進」の3つを重点分野として掲げています。これらの取り組みにより、スタートアップの数は2021年の約16,000社から2023年には22,000社に増加しました。大学発スタートアップやユニコーン企業の増加も見られ、計画の効果が徐々に現れています。
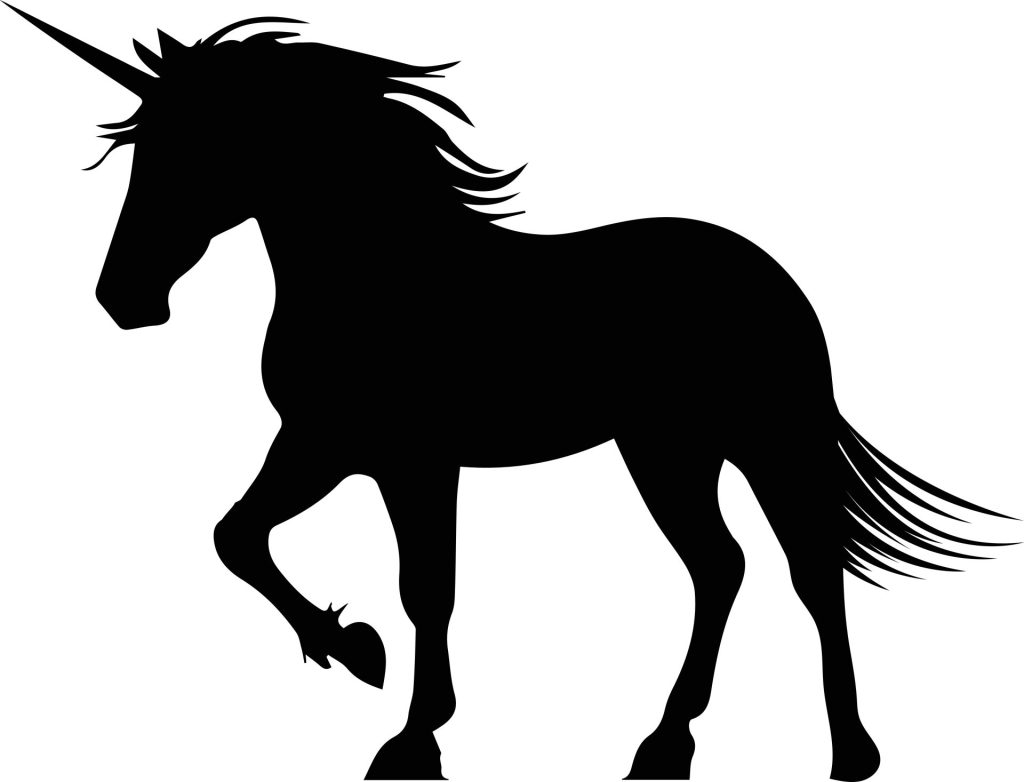
スタートアップの継続的な成長を支援するM&A
M&A(Mergers and Acquisitions: 合併と買収)は、スタートアップにとって重要なエグジット(出口戦略)のひとつです。スタートアップは、自ら成長を遂げた後、IPO(株式公開)を目指すだけでなく、大企業に買収されることで、市場展開を加速させる道を選ぶことができます。また、買収する大企業にとっても、スタートアップの革新的な技術やスピード感を取り込むことで、事業の成長や新しい市場への参入を促進するという大きなメリットが生まれます。
トプコンは、このM&Aを成長戦略の柱の一つとしてきました。1994年にアメリカの技術ベンチャー企業を買収したことを皮切りに、IT農業技術を持つ企業、最先端のGNSS(全球測位衛星システム)技術を持つ企業など、およそ40のM&Aを通じて、事業領域を大きく広げてきました。M&Aで先進技術を取り入れることにより、トプコンは農業、建設、ヘルスケア分野でのイノベーションを推進し、社会的課題の解決に貢献しています。
(参考資料)
経済産業省「スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する」
ハーバード・ビジネス・レビュー:「Research: The Average Age of a Successful Startup Founder Is 45」
日本政策金融公庫総合研究所「2023年度起業と起業意識に関する調査」
内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局「スタートアップに関する基礎資料集」
ダイヤモンド・オンライン「「GAFAM」除けば日米の株価成長は同じ?企業再編から考える米国経済の強さ」
経済産業省「令和5年度産業経済研究委託事業 (スタートアップの成⻑のための調査)調査報告書」
有斐閣「中小企業・スタートアップを読み解く」
日本能率協会マネジメントセンター「図解・ビジネスモデルで学ぶスタートアップ」







