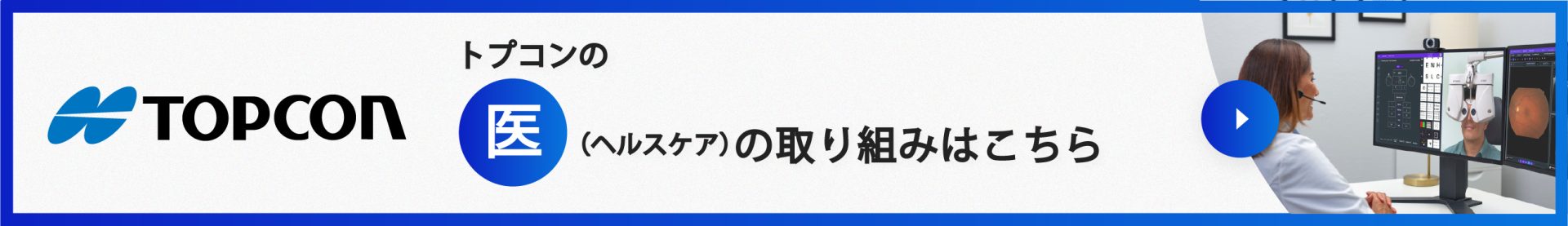目次
夜、外出先から家に帰ると多くの人がまず行うこと。それは、照明をつけることではないでしょうか。現代社会において、照明は私たちの生活に欠かせない要素の一つとなっています。照明の役割は、単に暗い場所を明るくして視界を良好にするだけではありません。照明の発する色味が、人々の心理状態や生産性に影響を与えることも、環境心理学などの様々な研究で報告されています。
この記事では、照明の明るさや色が居住空間や仕事環境にどのような影響を及ぼすのかを掘り下げていきます。
照明の色味は温度で表す
照明は、空間の明るさを変化させるとともに、色合いにも影響を与えます。照明による色合いは色温度で表し、絶対温度を示す単位ケルビン(K)を用います。色温度は、光源が発する光の色味を数値で表したものです。色温度の数値が低いほど赤みを帯びた暖色、高いほど青白い寒色を示します。
LED照明器具や電球型蛍光灯を購入するとき、電球色、昼白色、昼光色など、いくつかの光色に分かれています。蛍光灯の色温度は一般的に、電球色が3,000K、温白色が3,500K、白色が4,200K、昼白色が5,000K、昼光色が6,500Kで、LED照明もこれらと近い色温度に分類されています。白熱電球の色温度は約2,800K程度で、LED照明や蛍光灯の電球色のほうが、やや高い色温度に設定されています。
色温度は、照明だけでなく、太陽光の色を表す際にも用います。日の出後や日没前の太陽光は2,700K、平均的な正午の太陽光は5,200K、曇天の空では7,000Kです。太陽光と比較すれば、白熱電球や電球色の色温度は、夕陽のようなオレンジがかった温かみのある色、昼白色は正午の太陽光のような白っぽい色に近い色、昼光色は青みがかかった色になることが想像できます。

色温度が生活に与える影響
千葉大学の研究「身体運動時の光源色温度がヒトの生理機能と主観評価に与える影響」によると、色温度が、心拍数や血圧、直腸の温度を変化させ、集中力やリラックスといった心理的な効果にも影響を与えることが示されています。7,000Kの高い色温度では、心拍数や血圧が高まり、運動後の回復速度も遅れ、主観的な「リラックス」評価が低いことが分かりました。一方、3,000Kの低い色温度では直腸温の上昇が大きくなり、「眠さ」が最も高く、「集中力」が最も低いことが分かりました。5,000Kでは「やる気」が一番高まることも示されています。これらの結果から、昼間の自然光に近い色温度5,000Kが人間の身体運動に適していると結びつけています。

生活シーンに応じた色温度の選び方
それでは、実際に照明を購入するとき、どの色温度を選べばいいのでしょうか。それは、照明を設置する空間の使用目的によって異なります。一般的に勉強や仕事部屋など集中力を要する空間には6,500Kの高色温度が、寝室やリビングなどのリラックスを主体とする空間では3,000K以下の低色温度が推奨されています。色温度を選ぶ際は、照度も併せて考慮することが重要です。照度とは光の明るさのことで、単位はルクス(lx)です。

1941年に、オランダの物理学者アドリアン・クルイトホフ(Kruithof)が発表した研究によると、低い色温度(暖色系の光)は低い照度で、高い色温度(寒色系の光)は高い照度で、最も快適に感じるとされています。この法則は「クルイトホフ曲線」として知られ、その後も多くの研究者によって検証され、現在でも照明設計を行う際の重要な指針の一つとなっています。学会誌「医療福祉研究」に掲載された「照明の色温度と照度が室内環境評価に及ぼす効果」という記事でも、「読書」「勉強」などの活動的な場面では高色温度と高照度を用いることで、視覚的な識別能力を高め、効率的な作業を支援することが確認されています。
一方、「休息を取る」「仮眠する」などのリラックスする場面では、低色温度と低照度を選ぶことで、認知的にも身体的にも活動性が抑制され、よりリラックスしやすい環境が提供されることが報告されています。

切り替え可能な照明も登場
最近では、色温度や照度を一台で切り替えられる照明が人気を博しています。在宅勤務が増え、同一の空間で作業と休息の両方を行う人が多くなった現代では、これらの機能を持つ照明は特に便利です。例えば、作業中は6,500Kの明るくクリアな光で集中力を高め、仕事が終わった後は2,700Kの暖かい光に切り替えてリラックスすることが可能です。
照明の色温度や照度を意識することは、日々の生活に大きな影響をもたらします。照明一つを変えるだけで、毎日がもっと快適になるかもしれません。
【参考文献】
秀和システム「住まいの照明設計」
エクスナレッジ「世界で一番くわしい照明 最新版」
医療福祉研究「照明の色温度と照度とが室内環境評価に及ぼす効果」