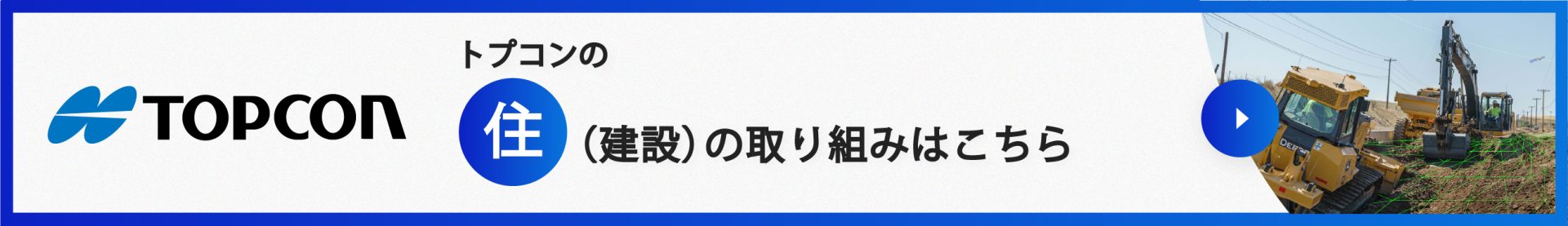目次
野球ファンなら誰もが注目しているメジャーリーグの大谷翔平選手の活躍が、連日のように報道されています。打球の上がり具合を表現するために、「バットから35度の角度で上がった打球が……」と、角度を用いて示されることがあります。円の1周が360度なので真上に上がると90度。35度なら、その約3分の1の角度で打球が上がったことを容易にイメージすることができます。

ところで、なぜ1周が360度なのでしょうか。単位は一般的に、1メートルが100センチメートル、1キログラムが1,000グラムといった具合に、10進法に基づいた区切りの良い数字で設定されていますが、360という数字は一見、そのような区切りの良さがありません。その理由は、「度」という単位の起源を紐解くことで明らかになります。
今回は、意外と知られていない「度」の定義やその歴史的な背景について解説します。
角度の単位「度」の定義と起源
角度(°)は、平面角を表す単位で、円の全周360度を分割して表します。1度は、円を360等分した1つであり、さらに、1度の60分の1が1分(′)、その60分の1が1秒(″ )です。円の全周を360度としたのは、紀元前2,000年以上も前にメソポタミアで都市文明を生み出した古代バビロニア人だといわれています。彼らは、太陽の運行を観察し、1年をおよそ360日とし、1日を24時間、1時間を60分とする60進法を用いたと考えられています。360という数は、多くの約数を持つのでとても便利です。1から10までの整数であれば、7を除くすべての整数で割り切ることができます。例えば、円を6分割して直線で結ぶと、正三角形が6個できます。つまり、半径で区切るだけで簡単に円を6分割できます。これをさらに半分に分割すれば12分割、2つ合わせれば3分割が可能です。円を4分割、8分割するのも容易に行えます。
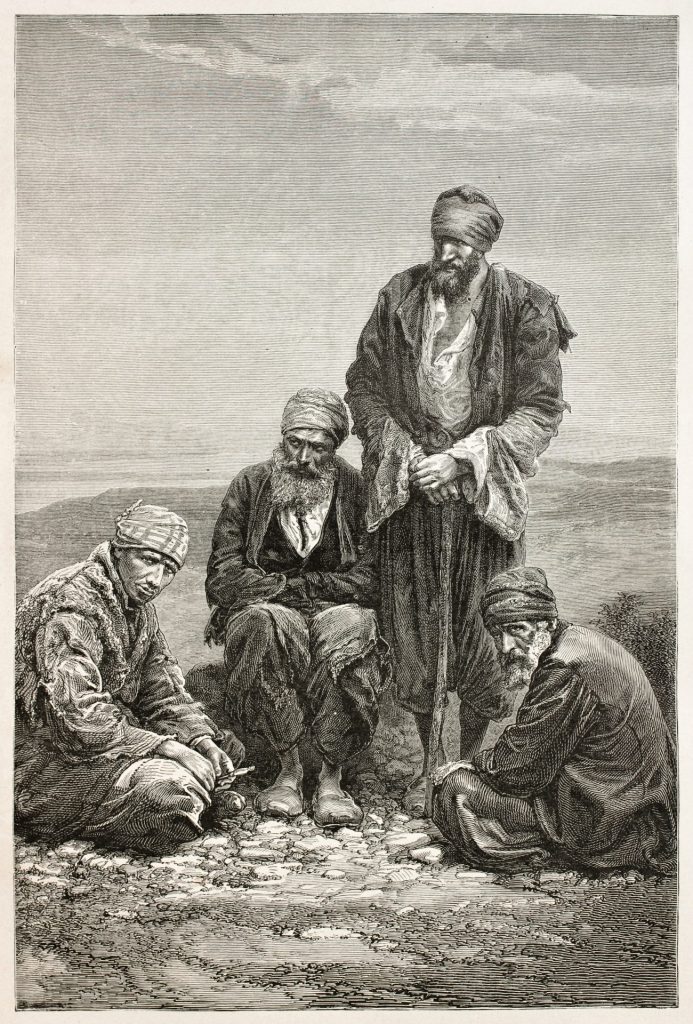
古代中国や日本でも、方位や時刻を表すのに十二支が使われていました。これも円を12分割する60進法が用いられています。一方、10進法は人間の手が10本あることに由来するとされています。数を数えるのにとても便利ですが、角度を表すには、時間を軸にした60進法のほうが合理的だったのです。
ちなみに、度の単位に使われる「°」という記号は、0に由来するとされています。17世紀頃から、整数部分と小数部分の区切りを上付きの0(零)で示す方法が用いられるようになり、角度においても、小数部分にあたる「分」や「秒」との区切りのために、「°」を用いられるようになったのだと考えられます。
「度」のほかにも正式な角度の単位がある!
世界にはさまざまな単位が存在します。例えば、長さの単位には日本の尺貫法やヨーロッパのヤード・ポンド法があり、以前は国や地域ごとに800種類以上の単位が使われていました。これらを統一するため、1875年にメートル条約が締結されました。メートル法とは、長さをメートル、質量をキログラムとする体系で、10進法を採用しています。これを機に、多くの国がメートル法に移行しましたが、メートル法導入後も分野ごとにさまざまなバリエーションが登場し、混乱を招くことがありました。そこで、1954年にパリで「国際単位系(SI)」が採択されました。
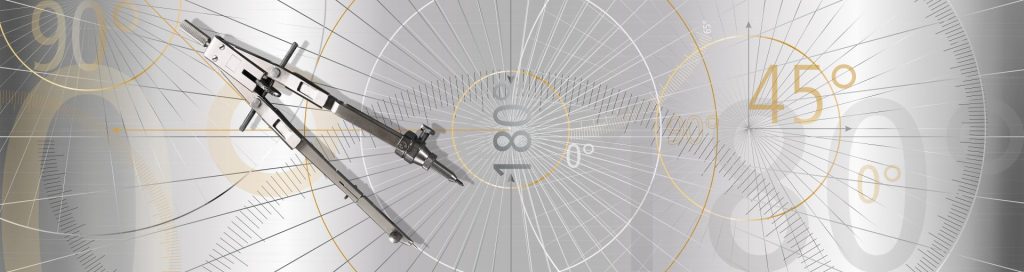
SIでは、平面角度の単位としてラジアン(rad)が採用されています。1ラジアンは円弧の長さがその円の半径と等しいときの中心角の大きさを指し、度で表すと、1rad=約57.3°になります。例えばホールケーキを分割する場合、ケーキの円周に沿って糸を巻き付けてから外し、人数分の長さに分割して印をつけます。これをふたたび巻き付ければ、糸の印を頼りに中心からナイフを入れて分割することができます。この考えに基づいた単位がラジアンです。しかし、なんとも手間がかかる分割法のような気がします。360度を人数で割って、その角度で切り分けたほうが、私たちにはイメージしやすいのではないでしょうか。

そこで、「度」のように古くから親しまれている単位は、SIでなくても使ってよいとされ、これらを「SI併用単位」として設定しました。ただし、角度の分以下の単位は10進法に統一し、小数点を使うことが推奨されています。例えば、6分は0.1度、60秒は0.01度と表記します。17度15分は17.25度となります。確かに、度までは60進法のほうがわかりやすいですが、小数点以下は10進法にしたほうが直感的にイメージしやすくなります。
角度を表すSI併用単位には、ほかに「gon」という単位もあります。gonは10進法を用いた単位で、1gonは、直角(90度)の100分の1(0.9度)を表します。gonはスイスなど、ヨーロッパの一部では現在も使用されています。
建築業界で欠かせない角度の測定
「度」という単位は、温度や糖度、方位、メガネの度数、音階などさまざまな場面で使われています。「度」を意味する「degree」は、もともとラテン語で「段」や「地位」、「程度」を表す言葉でした。角度が急になると段階や程度が上がるように感じるため、角度の単位に「度」が用いられたことは自然だったのかもしれません。
ただ、同じ角度でも日本で勾配を表す際には、通常は分数や%で表します。勾配は、水平の長さを基準の長さ1(または100%)とし、垂直の長さで示します。例えば、1/50(2%)の勾配は、水平に50cm進んだとき、1cm上がる(または下がる)坂道のこと。角度にすると約1.15度となります。
角度や勾配の測定は、建築や土木業界で不可欠です。建物や道路、橋など、あらゆる建設時には、正確な角度や勾配を求めなければ、安全に工事を進めることができません。私たちは小学生のときに分度器を使って角度を測定する方法を学びましたが、実際の測量の場面ではより高度な機器が使われています。
たとえば、測量機器の中で角度を測る機器を「セオドライト(経緯儀)」といいます。セオドライトは高精度ですが、開発当初は、ターゲットを正確に視準(目標に向けて調整)するための望遠鏡部分が回転しませんでした。これに対して、望遠鏡が回転するように使いやすく作られた機器が「トランシット」です。現在では、どちらの機器も望遠鏡が回転するようになり、違いがなくなりました。日本では「セオドライト」の呼称が多く用いらています。
角度を正確に測定するトプコンの機器
トプコンは「測量機の国産化」を目指して1932年に設立されて以来現在まで、分、秒の単位まで正確に角度を測定できる精度の高い測量機器を製造・販売しています。
角度を測る「セオドライト」、角度と距離を測る「トータルステーション」など、測量や建設の現場で三脚を立てて機械を覗き込んでいる人を見たことがある方は、一度はトプコンの製品に出合っているかもしれません。

トプコンの測量機器は、正確なデータを提供することで、安全かつ確実な施工をサポートします。最新の技術を駆使したトプコンの測量機器は、建築や土木業界において欠かせない存在となっています。
(参考文献)
学研教育出版「単位と記号」
秀和システム「図解入門 よくわかる最新単位の基本としくみ」
SBクリエイティブ「知っておきたい単位の知識 改訂版」
講談社「単位171の新知識 読んでわかる単位のしくみ」