目次
2018年に完成したアメリカ・テキサス州にあるロレックスのカスタマーセンターは、東京オリンピックのメイン会場である新国立競技場を設計した隈研吾によってデザインされました。スパイラル状にそびえる美しいガラスタワーの基壇部分には、敷地の高低差を解消し、ダラスのトラフィックから建物を守るため、日本の伝統的な石垣が採用されています。この石垣は、日本の築城の際に用いられてきた石積み技術を現地の花崗岩で再現したもので、この技術を代々受け継ぐ穴太衆が手掛けたそうです。石垣が、周囲の環境と建物を一体化させ、自然と建築の調和を生み出しています。
このように、海外でも高く評価されている日本の石垣には、どのような特徴があるのでしょうか。その技術や構造について詳しく探ります。
日本での石垣技術の進化と歴史
日本の石垣の歴史は、古墳時代にまで遡ります。現在、ほとんどの古墳は木々に覆われていて外観が見えにくいものの、多くの古墳には、表面に葺石(ふきいし)と呼ばれる石が敷き詰められています。また、内部の埋葬施設に、石を積み上げて造られた石室が使用されていることも知られています。その後、飛鳥時代から奈良時代にかけては、西日本の各地に古代山城が築かれ、平たい石を積み上げた石垣が用いられていました。しかし、技術の進展はあまり見られませんでした。
石垣技術が大きく発展したのは戦国時代に入ってからです。鉄砲の伝来が大きなきっかけとなりました。石垣の上に櫓を築いて鉄砲兵を配置することで、雨天時でも鉄砲を使用でき、防御力を飛躍的に向上させることが可能となったのです。
この時代の技術を象徴するのが、織田信長が1576(天正4)年から3年かけて築いた安土城です。安土城は総石垣の城として知られ、巨石を用いて高く積み上げられた石垣は、圧倒的な技術力を見せつけ、信長の権力を象徴するものでした。その後は、信長の家臣たちも、石垣と天守を擁した城を築くようになり、そして、1583(天正11)〜98(慶長3)年にかけて、豊臣秀吉が安土城を凌ぐ規模の大阪城を築き上げました。しかし、1615年に江戸幕府が「一国一城令」を発布し、新たな築城が禁止されたことにより、石垣技術の発展は江戸時代初期にほぼ完成を迎えました。

日本の石垣の種類と技術
日本の石垣は、独特の勾配と反りによって地震に強い構造を持ち、また美しさも兼ね備えていることが特徴です。石垣の積み方には、「野面積み(のづらづみ)」「打込接ぎ(うちこみはぎ)」「切込接ぎ(きりこみはぎ)」の3つがあり、それぞれ異なる特徴があります。「野面積み」は自然石や粗割り石をそのまま積み上げる手法で、見た目は粗くなりますが、風流で個性があり、荷重が偏らないように石をバランスよく配置したり、隙間を埋めるために小さな石を詰めたりする高い技術が必要です。「打込接ぎ」は、粗く割った石を加工して隙間が少なくなるように積み上げる方法、「切込接ぎ」は四角く加工した石を整然と積み上げる方法です。また、それぞれの積み方には、継ぎ目が横一直線になるように積む「布積み」(ぬのづみ)、不規則に積み上げていく「乱積み」(らんづみ)というバリエーションがあります。
石垣は、単に石を積み上げるだけではなく、土台や構造の工夫が重要です。石垣の構造は大きく分けて、土台となる「根石」、表面を覆う「築石」、その裏に詰める「裏込石」の3層から構成されています。土台である根石を安定させるために、盛り土や切り土によって地盤を整え、溝を掘って、場合によっては木材を使用して強化します。築石の裏側には飼石と呼ばれる大きな石やその隙間に小さな裏込石をぎっしりと詰めることで、雨水や地震の影響を最小限に抑えます。表面の築石の隙間には、「間詰石」を使うことで、石と石の直接的な衝突を防ぎ、耐久性を高めています。

石材は「石切丁場」から採取され、築城現場へ運ばれました。江戸時代には、全国の大名が築城に参加する大規模な土木工事「天下普請」が行われ、そこに運搬された石には家紋や記号が刻まれました。江戸城にはそのような刻印石が多く残されています。
石垣を守る最新の測量技術
石材を切り出し、運び、積み上げる技術は、長い間「秘伝」として継承されてきました。しかし、近年の文化財としての石垣調査や修理が進む中で、この技術が科学的に解明され、理解されるようになっています。現在、石垣職人(石工)の卓越した技は、「文化財石垣保存技術」として文化庁により保護されており、石垣の解体や修理に不可欠な技術とされています。
石垣の修理においては、まず現状を正確に把握することが不可欠です。石垣の健全性や変形部位、過去の修理歴を詳細に分析し、修理の必要性や最適な方法を決定します。従来は写真測量によって立面図を作成し、現地で検討を行っていましたが、近年ではレーザーによる3次元測量が導入され、石垣の形状や変形をより素早く、正確に把握できるようになりました。これにより、修理後には石材を元の位置に正確に戻すことが可能となり、修理計画の精度が向上しています。

さらに、東日本大震災や熊本地震での城郭石垣の被害を契機に、石垣の適切な管理と修復の重要性が再認識されています。最新の技術では、ディープラーニングを活用して石材を自動識別し、崩壊してしまった際でも、どの石をどの位置に戻すべきかを的確に判断できるようになりました。このような最新の技術により、地震などの自然災害に対しても、石垣を迅速かつ正確に修復することが可能になってきています。
トプコンの「だれでも」使える3Dレーザースキャナー
レーザーによる3次元測量は、建設現場を把握し、データとして残すのに役立ちます。ICTを活用した工事の普及に伴って、3Dレーザースキャンによって大幅に測量作業が効率化することに対しても理解が進んできました。一方で、3次元点群データを扱う技術者育成に対する不安から、建設会社では点群計測作業を外部委託するケースが多く見られ、必要なときに計測ができないといった課題があります。
トプコンの“だれでも使える”3Dレーザースキャナー「ESN-100」(愛称:“面トル”)は、自動整準、ターゲット自動検出などの機能によって、誰でも簡単に確実な3次元点群データの取得が可能な機器です。リアルタイムでデータを確認できるため、手戻りなく失敗しないことが特長。3次元点群計測をより身近に、そして簡単に始めることが可能です。
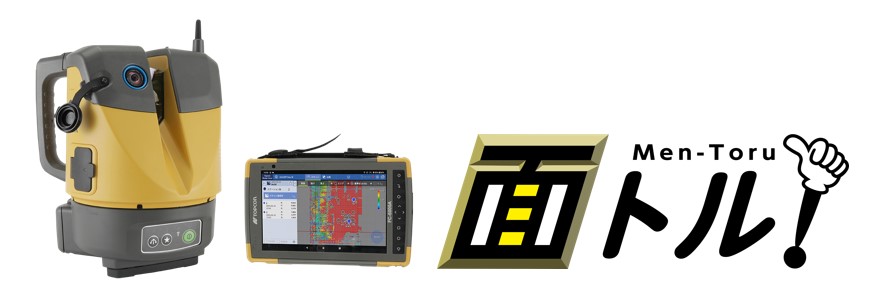
より多くの建設現場に3Dレーザースキャンが導入されていくことで、建設工事の効率化が進みます。トプコンはこれからも、建設分野の課題を解決する製品やソリューションを提供してまいります。
●トプコン「“だれでも使える”3Dレーザースキャナー『ESN-100』(愛称:“面トル”)と専用フィールドソフトウェア『Topcon Raster Scan』を発売」
(参考文献)
隈研吾建築都市設計事務所「Dallas Rolex Tower」
講談社「石垣の名城 完全ガイド」
二見書房「名城の石垣図鑑」
学研プラス「図説 戦う日本の城最新講座」







