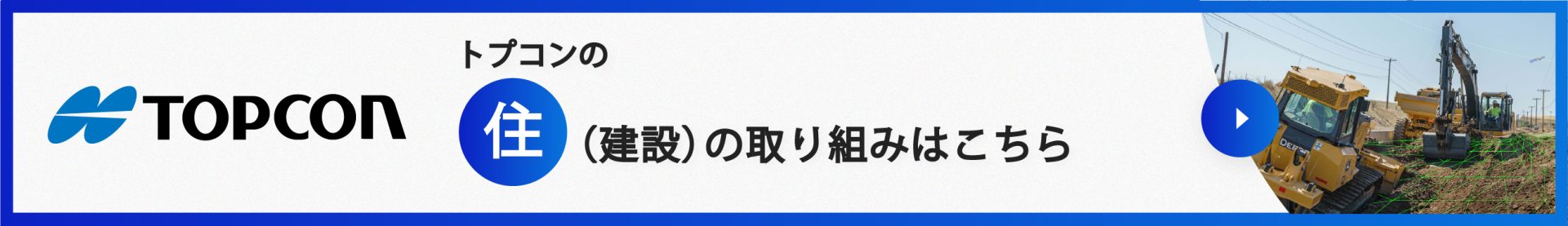目次
日本には大小含めて約3,000基以上ものダムが存在します。その中でも、日本を代表するダムといえば、日本一の堤高186mを誇る富山県の黒部ダムでしょう。観光スポットとしても有名で、その壮大な姿は一度見たら忘れられないインパクトを残します。
黒部ダムは、戦後の高度経済成長期に急増した電力需要を支えるため、関西電力が社運をかけて建設した巨大プロジェクトでした。当時の最先端技術を投入し、1956年の着工から7年の歳月をかけて建設されました。山岳地帯での工事は過酷を極め、その過程は映画の題材にもなりました。
黒部ダムに限らず、ダム建設は、その規模と技術の複雑さから、他の土木工事とは大きく異なる挑戦を伴います。ここでは、ダム建設が一大プロジェクトと言われる理由を紐解きます。また、2024年4月、国土交通省が発表した建設現場の効率化を目指す「i-Construction 2.0」が、ダム建設をどのように変えるのかを検証します。

ダムの役割とその歴史
ダムといえば、黒部ダムのように水力発電を目的に建設されると思う人も多いでしょう。しかし、実際にはダムには多様な役割があり、その歴史も古く、日本の土地と生活に深く根付いています。
日本でのダムの起源は、農地に水を供給する灌漑用のため池として始まりました。現存する最も古いダムは、奈良県の蛙股池(かえるまたいけ)や大阪府の狭山池で、今から約1,900年前につくられました。また、弘法大師が約1,300年前に築いたとされる香川県の満濃池は、その後も改良を重ねられ、今も灌漑用のダムとして活躍しています。
灌漑用水や水力発電といった役割は、ダムの役割のなかで「利水」に分類されます。利水とは、山が多い日本において、利用されずに下流まで流れ去ってしまう水をダムに溜めて活用することです。溜めた水を水源として確保し、渇水時に川の水量を増やすための放流もその役割に含まれます。水力発電は、放流時のエネルギーを利用したものです。ダムの水は生活用水、上下水道用水、工業用水としても供給され、雪国では消雪パイプや流雪溝に流す水を確保するための消流雪用水としても使われます。
一方で、ダムには大雨が降った際に洪水などの水害を防ぐ「治水」というもう一つの重要な役割もあります。ダムの貯水池に水を一時的に溜めて、下流に安全な量だけ放流することで、洪水被害を防ぐのです。このように、ダムは単に発電や灌漑だけでなく、多様な役割を持ち、私たちの生活や安全を支えている重要な存在です。

どうしてダム工事は難しいのか
ダムには様々な種類があり、その形状によって構造や特性が異なります。

・アーチ式コンクリートダム
ダムがアーチ状の形をしており、その曲面全体で水圧を左右の岩盤に分散させます。比較的少ないコンクリート量で高い強度を持たせることができ、狭くて深い谷に適しています。黒部ダムがこのタイプです。
・重力式コンクリートダム
ダム自体の重さで水をせき止めるシンプルな構造で、日本では最も一般的に見られます。
・バットレスダム
橋脚のような柱で、鉄筋コンクリート製の板を支える構造で、比較的軽量で材料の節約が可能なダムです。
・台形CSGダム
日本で開発された新しい型式で、コンクリート、砂、砕石を混ぜたCSG材料を台形に積み上げて固めたもので、建設コストを大幅に削減できます。
ダム工事の難しさは、これらのダムを単に建設するだけにとどまりません。実際には、多くの土木工事の要素が含まれており、その難易度は非常に高いものです。まず、ダムを建設するためには、山を掘削し、川の水を迂回させるためのトンネルを掘る必要があります。また、工事用車両が通行できる道路や橋の建設も不可欠です。特にコンクリートダムの建設では、短期間で大量のコンクリートが必要となるため、建設地近くの山を原石山として確保し、岩盤を削ってコンクリートの材料となる岩石を採取します。このために、破砕設備や材料を運搬するための設備も必要となります。さらに、給排水設備、電気設備、濁水処理設備などの仮設備も数多く設置しなければなりません。

加えて、ダム工事には複数のゼネコンが集まり、それぞれの専門技術を結集して協力し合うのが一般的です。およそ200人以上の作業員やJV(ジョイントベンチャー)職員が常駐するため、宿泊所や事務所の設置も欠かせません。このように、ダム建設は膨大な作業工程と設備投資、そして多くの専門技術者の連携が求められるため、非常に困難で長期間にわたるプロジェクトなのです。
i-Construction導入によるダム建設の展望とは
i-Constructionとは、国土交通省が推進する建設業の生産性向上と効率化を目指した取り組みで、ICT(情報通信技術)を活用して施工の自動化やデジタル化を進めるものです。2024(令和6)年には、新たな方針として「i-Construction 2.0」が策定され、建設現場のオートメーション化やデータ連携のデジタル化がさらに強化されました。
ダム建設においても、i-Constructionの導入が進んでおり、現場での施工プロセスが大きく変わりつつあります。例えば、レーザースキャナーなどの3次元測量や3D-CADを活用した設計・施工計画の策定、ICT建設機械による精密な施工管理、建設機械の自動化による、安全性と生産性の大幅向上などです。
ICT技術の導入によって測量・設計・施工・検査といった建設工事のフローが効率化し、品質もアップ。すでに各地の建設工事でi-Constructionが推進されており、ダム建設においても成果が何例も報告されています。トプコンは、i-Constructionの推進に積極的に取り組む企業をサポートするため、建設現場のデジタル化と自動化を支援する高度な測量機器やマシンコントロールシステムを提供しています。
ダムは建設して終わりではなく、その役割を果たせるよう持続的な管理を行ったり、観光資源としての活用など、完成後も私たちの生活のインフラとして深く関わり続けます。そんなインフラとしてのダム建設を支えるため、トプコンは「建設工事の工場化」を掲げ、i-Construction推進に取り組みます。
(参考文献)
・国土交通省「Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~」
・国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム総合管理事務所「何でもダム講座」
・国土交通省近畿地方整備局「川上ダム建設事業におけるICT技術を導入した工事について」
・株式会社実業之日本社「この一冊で「ダム」と「河川管理」が見えてくる!
・SBクリエイティブ「ダムの科学 改訂版 知られざる超巨大建造物の秘密に迫る」