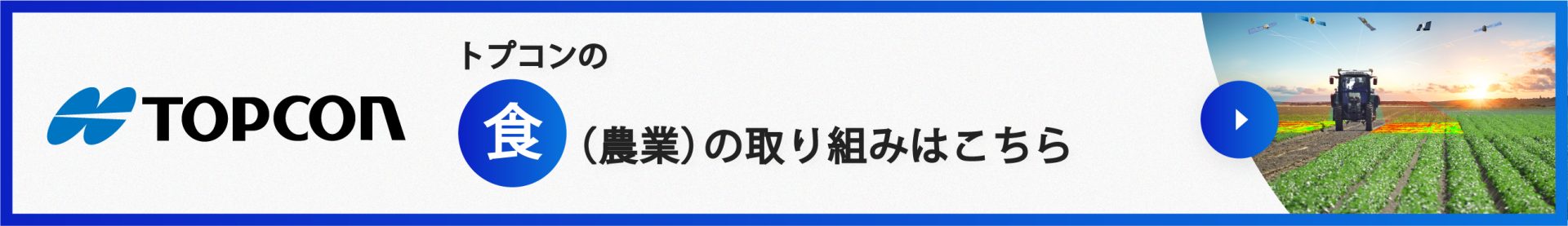目次
現在、日本の各地で、生き物に配慮した米づくりが行われています。この取り組みによる米は一般的な米よりも高付加価値化しており、世の中の環境保全への関心がうかがえます。生き物だけではなく、農家にとってもメリットがある環境保全型の米づくり。その取り組みを紹介します。
6,000種超の田んぼの生き物が減少の一途
ドジョウ、ゲンゴロウ、ダガメ、タニシ、アメンボ、トンボ、アマガエル、ミミズ、サギ、コウノトリ、トキ、ガン…、水が張られた田んぼ「水田」には、多くの生き物が生息しています。その数は、プランクトンから鳥類までを範囲とすると、6,000類を超えるといわれています。水田は、農地であると同時に、生物多様性の豊かな環境を誇る場でもあるのです。
ところが、水田の面積は、1960代から2000年代までの間に約24%減少。さらに、土の水路がコンクリートで覆われることなどによって、生き物が多く生息する水田・水路は、この50年で半減してしまいました。それに伴って多くの生き物は行き場を失い、生息数が減少。絶滅の危機に瀕している生き物が増えています。
生物多様性保全に関する地球規模の条約としては、最も早い1971年に採択された、湿地の保全に関する国際条約「ラムサール条約」があります。この条約では、水田やその周辺の水環境は、保全すべき重要な水環境(湿地)の一つとして定義されています。しかし、生き物の生息地としても重要な湿地は、いまだに工場や宅地等へ開発され、世界中で減少しています。一度開発してしまうと、どのような努力をしても完全に取り戻すことが不可能といわれていることから、生息場の減少による生息数の激減は非常に嘆かわしいことです。そんな中、この非常事態を我が事と捉える人々によって、多くの生き物の住みやすい環境を守ろうとする活動が各地で行われています。

「ふゆみずたんぼ」はイイこと尽くし!?
活動の一部は、農林水産省による「生きものマークガイドブック」に紹介されています。農林水産省が推進する取り組み「生きものマーク」とは、「農林水産業の営みを通じて守り育む取り組みと、その産物等を活用した発信や環境教育などのコミュニケーション(必ずしもラベルを産物に貼ることを条件としているわけではありません)を表す言葉です」とのこと。
例えば、宮城県大崎市では、渡り鳥のガンなどの水鳥が休んだり餌を取ったりできるように、水田に冬も水を張る 「冬期湛水(とうきたんすい)」 、通称「ふゆみずたんぼ」を行っています。ガンの数は減少しており、限られた水場に集中すると、そこで伝染病が蔓延した際に絶滅する恐れもあります。「ふゆみずたんぼ」はこうした水鳥が暮らす環境保全の取り組みとして始まりました。
取り組みの結果、「ふゆみずたんぼ」はガンだけではなく、水辺の生き物にも、さらには米にも、農家にも良い効果をもたらすことが判明しました。集まった水鳥のふんや藁をイトミミズなどが分解することで、天然の堆肥ができます。そして、ここで収穫された米はブランド米「ふゆみずたんぼ米」として販売され、農家の収入を安定させています。2017年には、鳥類と共生する持続可能な水田農業の価値が認められ、「大崎耕土」の一端として世界農業遺産に登録されました。関係者にとって誇るべきことといえるでしょう。
「ふゆみずたんぼ」は、今では各地で実施されており、兵庫県豊岡市ではコウノトリ、新潟県佐渡ではトキ、佐賀県伊万里市ではツル等が生息しやすい自然環境の保全にもつながっています。2011年度より、国からの環境保全型農業直接支払交付金の支援が行われるようになったことで、生き物にとっても、農家にとってもメリットのある農法として、今後ますます広まっていくかもしれません。
小さな命と自らの暮らしを守るための努力と工夫
「田ネコ」とも呼ばれる対馬にのみ生息する天然記念物『ツシマヤマネコ』が、50年前の300頭から約100頭まで激減したことで、動き出した取り組みもあります。活動のはじまりは、2006年に開かれた対馬市上県町佐護地区の座談会。勉強会は度々開かれ、仲間が増えたことで2009年には研究会が発足しました。2012年には、全国環境保全型農業推進コンクール奨励賞を受賞する等、取り組みが認められるまでに発展していきました。
田ネコは、田んぼの小さな生き物を餌としています。そのため、取り組みでは田ネコの餌場や隠れ場所となる、また餌となる生き物にとっても棲みやすい環境となる田んぼを目指しています。農薬・除草剤の不使用や減量、魚や生き物が田んぼや川を行き来できる水路やビオトープの設置、生き物調査や自動撮影調査等を実施しながら、米づくりが行われています。
収穫した米は、デザインの力を活かしてネコが描かれたパッケージで全国へ産直。活動への理解者や応援者が増え、認定田は年々増加しています。販売量は、2011年4,300kg、2023年25,000kgと約5.8倍に。2012年からはオーナー制度をスタートさせ、12口から2023年には143口にまで増えました。理解や人気を継続、拡大させるために、課題・活動内容・意義をイラストや端的な言葉で表現したり、キャラクターのグッズ展開、農家のリアルやツシマヤマネコの暮らしを動画等で伝えるなど、さまざまな工夫を凝らしています。

環境を保全して作られた米は高付加価値
生き物に配慮して環境を保全しながら作られた米は、一般的な慣行栽培の米「慣行米」と比べると価格は上がりますが、農林水産省が農林水産業における生物多様性の経済価値を試算したところ、多くの人が保全に対してお金を支払ってもよいと考えていることが判明しています。例えば、ツシマヤマネコに支払ってもよい額は、一世帯あたり2,423円/年、その全国総額は1,259億円になります。この金額は仮想市場評価法で算出された金額で、アンケートにより価値を評価しています。
農林水産政策研究所では、2010年度と2021年度に、環境保全型農業によって生産された米を対象に調査を実施した結果、どちらの年も、慣行米と一定の価格差を生み出せると確認されました。価格差は、5㎏で、2010年度では661円、2021年度では917円と増加。各地では、より一層の付加価値の付与を狙って、生き物に配慮した生産の取り組みを推進させるための認証制度を導入し、認証ラベルを使用するところも出てきました。
環境に配慮した米づくりは、一過性のブームではありません。JA全農が、2030年産までに、取り扱う米の全量を環境に配慮した米とすることを目標に掲げていることからも、環境保全の取り組みはこれからも広がっていくでしょう。ただし、問題がないわけではありません。付加価値の高い米であっても、直面するのは、やはり、日本の問題である就農人口の減少。そして、後継者不足です。そんな状況を救えるのが、農作業における省力・軽労化を可能にし、未経験者でも熟練者並みの効率の良い作業を実現できるスマート農業。トプコンは、目の前のことだけではなく、広い視野をもって農業を進めていきたいと望む農家をスマート農業でサポートしていきます。
参考文献
WWFジャパン「水田・水路の生物多様性と農業の共生プロジェクト」
WWFジャパン「失われる命の色 田んぼの魚たちと自然を守るために」
琵琶湖環境部「「田んぼの生きもの全種データベース」を公開しました」
環境省『ecojin(エコジン』「ふゆみずたんぼ| ecojin’s EYE」
九州地方環境事務所「ツシマヤマネコと共生する暮らしのヒント」
農林水産省「「生きものマーク」米の取組の追跡調査 ―2010年調査と比較して―」
九州地方環境事務所「田ネコの暮らす田んぼとお米【対馬地域】」
地球循環共生圏「新たな仲間や応援者を巻き込むための、 伝え方・共感の生み方ツシマヤマネコ米販売の実績」
時事ドットコム「環境負荷低減「見える化」農作物などにラベル表示ー農水省」