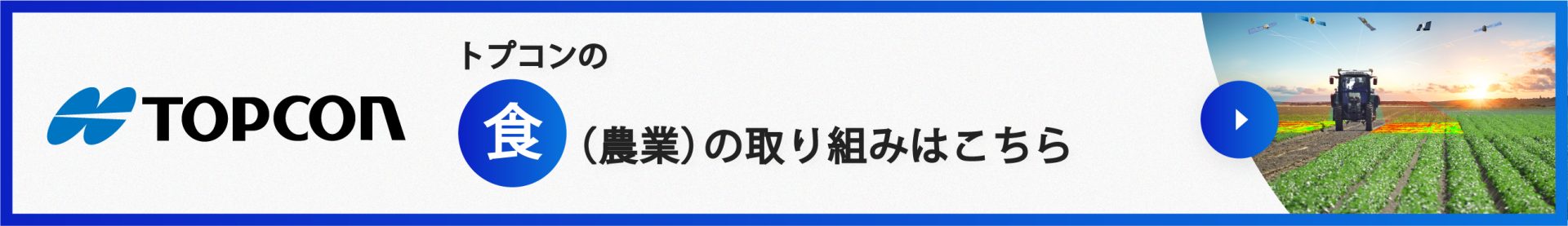目次
国の方針「みどりの食料システム戦略」をご存じでしょうか。農業において、鉱物資源や化石燃料を原料とする化学肥料の使用量を、2050年までに30%まで低減する目標を掲げている政策です。SDGsの気運が高まっていることもあり、作物の生長に欠かせない肥料には、農業関係者以外からも注目が集まっています。土のため、地球のため、ひいては私たち自身のためにも、化学肥料の低減には、誰もが関心を抱かなくてはならない時代に入ってきています。
そもそも化学肥料は、なぜ低減が必要?
農業にとって、土の環境は最も重要といえます。ただし、土を耕すだけでは、美味しい作物は育ちません。良好な生長のために不可欠なものの一つが、肥料です。肥料に多く含まれているのは、植物の生育に必要な量が多い成分として、植物の葉や茎の生長を促す「窒素(N)」、開花や結実を促す「リン酸(P)」、根の発育を促す「カリウム(K)」。
上記の窒素・リン酸・カリウムほどではないものの必要量が多いのは、肥料成分の吸収を助ける「カルシウム(石灰)」、植物の新陳代謝を活発にする「マグネシウム(苦土)」、葉緑素の生成を助ける「硫黄」、その他、健康的な植物の生長に役立つ鉄、銅、亜鉛等、必要量が微量な要素もあります。
肥料の種類は、油粕、魚粉、米ぬか、骨粉など、生物由来の有機物質から作られる「有機肥料」と「化学肥料」の二つに大きくは分けられます。化学肥料は、鉱物資源や化石燃料を原料にして化学的処理によって工業的に生産される肥料です。低価格で、品質は安定、速やかに効果を発揮するというメリットを持つことから、作物の増産に向いています。これまでの農業の現場では世界中で多用され、今後の世界的な人口増加において、食料生産を支えるには欠かせないともいわれています。

しかしながら、懸念材料となるのが、環境への負荷です。ひとつは、化学肥料の生産から使用過程における温室効果ガスの排出量。また、過剰に肥料をまくことで植物が肥料をすべて吸収できずに地下水へ流れ出て、環境汚染につながることも懸念されています。化学肥料が流れ出た地下水は自浄作用による水質の改善が期待できないため、回復が困難なのです。
さらに、土の中の微生物が減少することによる地力の低下も指摘されています。国連食糧農業機関(FAO)は、化学肥料と農薬の影響で、地球にある土壌の33%以上がすでに劣化していると報告しています。付け加えるなら日本は、化学肥料のほぼ100%を海外に依存しています。国際輸送によってCO2排出量が多くなっていることも忘れてはいけないことです。
消費者も取り組める「みどりの食料システム戦略」
現在、持続可能な農業を目指す国々では、化学肥料の削減への取り組みが喫緊の課題となっています。日本も、もちろん取り組んでおり、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、2021年に「みどりの食料システム戦略」を策定、2022年7月には「みどりの食料システム法」を施行しました。
目標は、2050年までに、化学肥料使用量を30%低減すること。そのために「有機物の循環利用や施肥の効率化・スマート化」を推進しています。農水省によると、2022年の化学肥料使用量は81万t(窒素・リン・カリウムの総量、生産数量ベース)で、基準年である2016年と比べると約11%減少しました。目標の30%低減を達成するには、63万tまで下げる必要があります。
肥料を使う生産者だけではなく、消費者も協力は可能です。環境に配慮した生産手法によって生産された農作物を購入する。それだけです。一方、農水省のアンケートからは難しさが窺えます。環境に配慮して生産された農作物に対して、「このような農産物を購入したい」と回答する人は約8割。一方で「購入したことがない、また今後購入しない」理由として、「どれが環境に配慮した農産物かどうかわからないため」と答えた人が6割以上という結果が出ているのです。「見える化」を実現する等、消費者が選択しやすい環境整備が急がれます。

コーヒー、昆虫、コウモリ、食器も有機肥料を作り出す
化学肥料の使用量低減のために、代替肥料になるのが有機肥料です。有機肥料は土の中で微生物によって分解され、無機物となって効果を緩やかに発揮します。最近では、持続可能な農業を支えるにあたり、環境に優しく、ユニークな素材を使った有機肥料が増えつつあります。キーワードは廃棄物の「リユース(再利用)」です。
例えば、リン酸や窒素を含むカニやウニの殻、魚のアラ等々が有機肥料に活用されています。カルシウムをはじめ、マグネシウム、鉄等の微量元素を含むコーヒーかすも役立ちます。カブトムシや食用コオロギといった昆虫の飼育過程で出る、排せつ物と木屑や植物組織片が混ざった「フラス」も、窒素・リン酸・カリウムを豊富に含んでいます。コウモリのふんが洞窟内に堆積し、化石化した「バットグアノ」は、リン酸、カルシウムを豊富に含む有機肥料としてネットからも手軽に購入できます。
珍しいところでは、食器も使われます。磁器の一つであるボーンチャイナに多く含まれる「リン酸三カルシウム」は、肥料の重要な成分であることから研究開発された末、2022年に農林水産省から肥料として認定されました。
有機肥料の市場が拡大すると予想されることもあり、各々の立場から、各々の動き方をする企業等が増えつつあります。ここ数年、輸入する化学肥料の価格高騰に悩まされている日本では、コスト削減のために有機肥料へ転換する農家も増えています。身近なものから生まれる有機肥料が、農家はもちろん、家庭菜園を楽しむ人にも、ますますの関心事になっていることから、「みどりの食料システム戦略」の目標達成にも期待が集まります。

今後の注目は、未利用資源、土壌微生物、スーパー品種
2050年までの化学肥料使用量30%低減に向けて、さらに企業、大学などでは研究が進められています。例えば、未利用資源から機能性の高い肥料成分を回収する技術開発。その一つが、家畜の排せつ物(畜ふん)で育ったイエバエの幼虫に、有機肥料を1週間程で生み出させる技術です。
畜ふんにイエバエの卵を蒔くと、8時間程で幼虫になります。幼虫が畜ふんを消化したものをペレット化すれば、有機肥料ができます。この取り組みは、温室効果ガスの発生、地下水や河川の汚染を抑えられるメリットを持つことからも、みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業の認定を受けています。
その他、大部分が謎に包まれている土壌微生物の機能を完全に解明し、フル活用することで、化学肥料や農薬に頼らない農業を目指す研究も進んでいます。肥料利用効率が非常に高い「スーパー品種」の育種と普及も進められています。
同時に、スマート農業によって肥料の使用量を最適化することで環境負担を減らす取り組みも進んでいます。作物の生育状態や前年度のデータに応じて肥料の使用量を調節すれば、肥料のやりすぎを防ぎ、環境負担と農家の経済負担を低減することができます。
トプコンはレーザー式生育センサーや農機の自動操舵システム、データの一元管理によって、効率的な施肥を実現します。今後も技術開発を進めることで、サステナブルな農業を支援していきます。

<参考資料>
農林水産省「『みどりの食糧システム戦略』KPI2030目標の設定について」
農林水産省「みどりの食料システム戦略に基づく取組の進捗状況」
農林水産省「食料・農業・農村政策審議会 企画部会 議事録」※地球環境小委員会 合同会議 第29回
資料2 みどりの食料システム戦略中間取りまとめ(案)(参考資料)【分割版】その6
国連広報センター「『世界土壌デー(12月5日)』および『国際土壌年』開始に寄せる 事務総長メッセージ」
農林水産省「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践・見える化(情報開示)」