2025(令和7)年4月1日、国土地理院で管理する基本基準点(電子基準点、三角点、水準点)の標高成果(公式に定められた標高値)が改定されました。これにより、三角点では宮城県牡鹿半島で最大+57cm、北海道知床半島で-67cmの改定となりました。どうして標高が変わるのでしょうか? その理由を詳しく解説します。
今まで標高はどうやって測っていた?
日本における標高とは、平均海面からの高さのことを指します。標高の基準となるのは、東京千代田区の国会前庭園に設置された日本水準原点です。この原点は東京湾平均海面を基準に24.3900mと定められています。この原点を基準に水準測量を行い、日本全国に約1.7万点の水準点(標高の基準となる測量基準点)が設置されています。水準測量とは、既に標高が分かっている点と、求めたい点の両地点に3mの標尺(目盛りが刻まれたものさし)を立て、それらの間にレベル(目盛りを読む光学機器)を水平に設置して、標尺の目盛りを読み取ります。そして、2つの標尺の目盛りの差から高低差を求め、標高を決定します。この方法は直接水準測量と呼ばれ、標高の決定には非常に高い精度を誇ります。

一方で、直接水準測量には時間がかかるという課題があります。レベルで目盛りを読み取るとき、標尺との距離は簡易水準測量でも最大で80mと決められています。水準点は全国の主要道路などに約2kmごとに設置されていますが、2km先に新たな水準点を設置するためには、何十回もの直接水準測量を繰り返す必要があります。日本全国での水準測量を完了するには10年以上を要し、その間に発生した地殻変動による誤差が蓄積してしまいます。また、東京を基準に行われるため、東京から離れるほど測定誤差が距離に比例して累積するというデメリットもあります。これらの課題を解消するために、衛星測位(GNSS測位)を活用した新たな標高決定手法が導入されました。

衛星測位による標高改定の必要性
衛星測位とは、位置が既知のGNSS衛星を、いわば動く基準点として利用し、4機以上の衛星からGNSSアンテナまでの同一時刻における距離を知ることにより、観測点の位置を決定するものです。日本全国には、衛星測位を行うための電子基準点が約1,300ヵ所設置されています。衛星測位によって得られる位置情報には「高さ」の情報も含まれますが、このときに得られる「高さ」は「標高」ではなく「楕円体高」と呼ばれます。
楕円体高とは、地球がわずかな楕円だと仮定したときの仮想的な基準面(地球楕円体)から測定する地点までの高さのこと。標高は平均海面から測定地点までの高さを指すため、楕円体高と標高は基準となる位置が異なります。そこで衛星測位による標高を求めるために、従来法でいう「標高」の基準となる平均海面を陸地にも仮想的に延長した「ジオイド」を基準にします。
実は、地球の重力は場所によって異なるため、平均海面は細かく見ればデコボコしています。このデコボコとした面が「ジオイド」と呼ばれ、標高はこのジオイドからの高さとして定義されます。
今回の標高改定に先立ち「ジオイド2024日本とその周辺」が策定されました。このジオイドは重力の測定で求める「重力ジオイド」という方式のみで算出しています。これ以前の日本のジオイドは地上重力データの観測時期が古く、位置情報の精度が低いことなどから、重力ジオイドの精度が高くなかった(約8cm程度)ため水準測量によって求められた標高との差分から算出する「実測ジオイド」で補う方式を使用していました。しかし、先述のように水準測量には地殻変動の影響や遠隔地での誤差が蓄積される問題があります。そこで、「ジオイド2024 日本とその周辺」は、水準測量に由来する誤差が含まれない重力ジオイドのみを使用する方式に移行し、さらに航空機に搭載した重力計を使用して重力観測することで精度は約3cmに向上しました。
これからの標高と今までの標高の違い
今回の改定により、電子基準点で得られた楕円体高と、新たに定めた「ジオイド2024日本とその周辺」から新しい標高が決定されます。改定前は、電子基準点の標高は水準点から電子基準点横に設置された付属標の高さを水準測量によって求め、アンテナまでの高さを加えて決定していました。しかし今後は、電子基準点でGNSSから得た楕円体高から「ジオイド2024 日本とその周辺」によるジオイド高を引いた値が標高となります。この標高を基準に、全国の水準点や三角点の標高を水準測量によって決定します。このようにして求められた標高が、2025(令和7)年4月から公開されました。
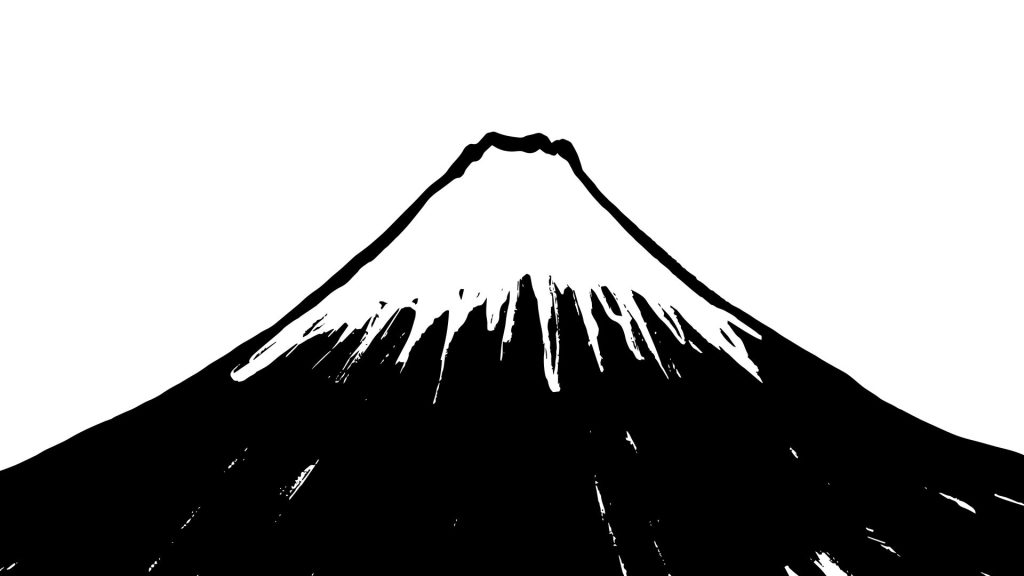
この公開に先立ち、富士山頂にある2級三角点の標高測定が実施されました。電子基準点を用いて三角点の標高を決定する手順は、国土地理院が公開した動画で確認できます。この測量にはトプコンのレベルが使用されました。三角点の新しい標高成果は、現在の標高成果(3,775.51m)より5cm高い3,775.56mとなりました。この三角点は、富士山の最高地点よりも低い位置にありますが、富士山の標高は、今回の測定結果を四捨五入し、従来通りの3,776mのまま変更はありません。
●富士山頂測量に用いられた機器

標高成果改定によるメリット
標高成果改定により、最新の標高を用いて高さ情報の管理が可能になるとともに、衛星測位の活用によって、測量や公共工事等の効率化・生産性向上、新たなサービスの創出が期待できます。地殻変動で累積した現実と標高成果のズレが解消され、「ジオイド2024 日本とその周辺」と衛星測位を用いることで、従来よりも迅速かつ高精度に、現況に即した標高が取得可能になります。
例えば、2016(平成28)年の熊本地震の際、地殻変動後、電子基準点の楕円体高を取得し、標高成果を改定するまでに約1ヵ月を要しました。その後、影響のあった周囲の電子基準点36点の標高を水準測量で算出し、利用可能になるまでには約5ヵ月を要しました。しかし改定後は、楕円体高を取得した時点(約1ヵ月後)で、3級水準測量(6km以上、付属標は1級)に適用できる標高の提供が可能になります。
また、水準測量の起点から離れるほど蓄積していた標高の誤差が解消され、標高の時点(元期)が明確となることで、標高の整合性が全国一律に向上し、電子基準点による全国の標高の時間変化の監視が可能となるとともに、「4次元国家座標(測量成果の時間管理)」の実現に向けた基礎が整備されます。ただし、従来の水準測量も短距離測定においては、精度とコストの両面で優位性を持ちます。今後は、衛星測位による標高と水準測量を組み合わせることで、より精確な測量が可能になるでしょう。
(参考文献)
国土地理院「令和7年度 全国の標高成果の改定」
国土地理院「衛星測位を基盤とする三角点「富士山」の新しい標高~基準点の標高成果の改定に向けた取組~」







