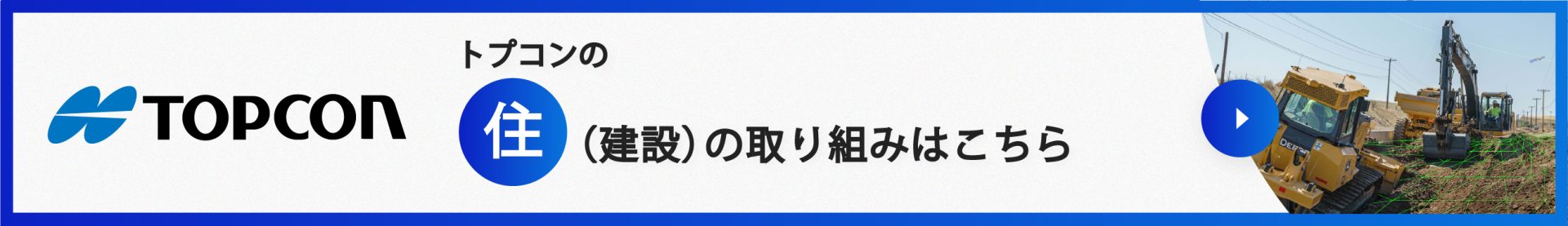目次
日本は、国土面積の67%が森林に覆われており、世界有数の森林大国として知られています。地形図を見れば等高線が密集している場所がたくさんあり、日本の土地の高低差が激しいことがわかります。日本一の高さを誇る富士山の標高は3,776m。本州の中央を走る日本アルプスには3,000m級の高峰が連なっています。これらの標高は、どこを基準(標高0m)に設定し、どのようにして測定されたのでしょうか。
日本では明治時代初期から、土地の高さを測るための基準として「水準点」が用いられてきました。水準点は日本中に設置されており、建築や土木工事を計画・実施する際にも重要な役割を果たします。しかし、これら水準点が実際にどこにあるのか、どのように設置されたのかについてはあまり知られていません。
そこで本記事では、国土の高さを測る上で欠かせない水準点と、現代の国土の高さを測る技術について解説します。

日本の“高さの基準”は、重要文化財に指定されている
標高とは、海面からどれだけ高いかを示す数値のことで、「海抜」とほぼ同じ意味で用いられます。海面の高さは、気象条件や天体の動きによって絶えず変化しています。そのため標高の基準(標高0m)には、一定の期間にわたって観測した海面の高さの平均値(平均海面)を算出して設定します。日本では、1873(明治6)年から約6年間、東京隅田川河口(霊岸島)で海面を測定し続け、平均海面を導き出しました。現在、一部の離島を除き、この平均海面を日本の標高0mに設定しています。
1891(明治24)年には、日本の標高の基準を明確に示すための「日本水準原点」が、かつての陸地測量部内(現在の国会前庭)に造られました。地震などで動かないように、地下約10m以上深くまで強固な基礎を打ち、材料には温度変化で伸縮しないコンクリートや煉瓦、硬石が用いられました。最も大切な目盛りとなる部分には、堅くて丈夫な花崗岩台石に、山梨県産の水晶板がはめ込まれました。さらに、石造の小さな西洋風の建物(日本水準原点標庫)に収められ、普段は扉が閉じられています。日本水準原点と日本水準原点標庫は、100年以上にわたり日本の標高の基準としての役割を担い続けてきたことから、近代測量150年の節目となる2019(令和元)年に、測量分野の建造物で初めて国の重要文化財に指定されました。同年には土木学会選奨土木遺産にも認定されています。

「水準点」を用いて国土の高さを測る方法とは?
日本水準原点のゼロの目盛りの標高は、現在24.3900mに等しいとされています。1891(明治24)年の設置時には、24.5000mでしたが、関東大震災や東北地方や太平洋沖地震による地殻変動、また、測量法施行令制定により、その都度改訂されてきました。標高を測る際には、この日本水準原点と、もう一つの地点にそれぞれ標尺(長さ3mのものさし)を立て、両地点間にレベル(水準儀)を水平に設置します。そして、レベルから各標尺の目盛りを読み込み、その高低差から標高を求めます。例えば、ある地点Aが日本水準原点より1m高い場合、A地点の標高は、日本水準原点の標高24.3900mに1mを足した25.3900mとなります。
※国土地理院「水準測量」

このようにして標高を求める手法を「直接水準測量」と呼んでいます。日本水準原点から離れた地点でも正確に標高が測定できるように、約100mごとに直接水準測量で高低差を測定しながら進み、順々に標高を定めた水準点が設置されています。主に主要国道沿いの約2kmごとに一等水準点を、100〜150km間隔の地盤が強固な全国80ヵ所には基準水準点を設置。そのほか二等水準点も含めると全国に約16,000ヵ所の水準点が設置されています。
水準測量は、河川や道路、港湾、下水道、鉄道など、正確な高さの値が必要な工事で利用されます。高低差の位置を明らかにすることで、地形を均す工事や、水を下流へと流す水路建設などで、どの土をどれだけ削り、どこを埋めればよいのかなどを判断することができます。また、地下水の組み上げなどによる地盤沈下の監視や、震災後の復興作業における高さの基準としても活用されています。
GNSSを利用した電子基準点の登場
それでは、山の標高はどのようにして測定するのでしょうか。直接水準測量でも可能ですが、膨大な労力と時間が必要になるため、実際にはトータルステーションなどの測量機を用いて角度と距離から高さを求める「間接水準測量」が一般的に採用されてきました。日本には、高さを示す水準点のほかに、緯度・経度・標高が記録された「三角点」も至るところに設置されています。三角点は、主に見晴らしのよい山の上に設けられていることが多いため、山上の三角点と地上の水準点または標高がわかっている三角点との角度を求めることで標高を測定するのです。
※詳しくは→地形図に記されている△の中に黒点がある記号は何?
しかし、三角点が設置されている場所は、必ずしも山の最高点とは限らず、正確な標高の測定が難しい場合がありました。また、地殻変動の影響で変わることもあるため、近年になって山頂の標高が判明したり、記録が改訂されたりしているケースがあります。例えば、富士山の標高も過去に何度か見直しが行われており、2014(平成26)年には、以前の測定からわずかに低い3776.12mに修正されました。これは、従来の三角点とは異なる場所に新たに設置された電子基準点のデータに基づく標高です。
電子基準点は、GNSSを利用して位置を測定するためのものです。地震や火山活動による地殻変動を監視するための重要な観測点であり、測量の新たな基準として用いられています。電子基準点には衛星からの電波を受信するアンテナ、受信機が内蔵されたステンレス製のピラーが立っているため、水準点や三角点よりも発見しやすいでしょう。この電子基準点の整備には、トプコンも大いにかかわっています。建設業や農業の自動化にも必要な衛星による測位技術は世界中で注目されており、トプコンは東南アジアなどで電子基準点の整備に協力しています。
測量技術の進化とともに、標高を測る手法も多様化してきました。街で、ハイキングで、「標高〇〇m」の文字を見かけたら、「この標高はどうやって測ったんだろう」と思い出してみてください。
<参考資料>