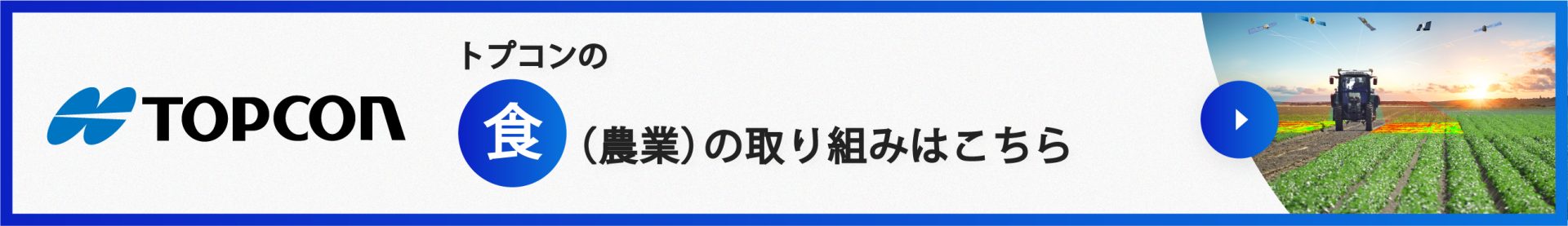目次
日本の農業は今、転換期を迎えています。JA全中(一般社団法人全国農業協同組合中央会)の報告によれば、基幹的農業従事者の数は、2020年には136万でしたが、2030年には83万人、2050年には36万人(30年間で約7割減少)となる見通しが示されています。このような急激な減少が続けば、農地の維持管理は難しくなり、食料供給の安定に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。
このような状況下で注目を集めているのが、「CSA(Community Supported Agriculture、地域支援型農業)」です。CSAは、生産者と消費者が直接つながり、農業を支え合う仕組みです。消費者が農作物の代金を前払いすることで、生産者は資金繰りの安定を図ることができ、持続可能な経営を実現できます。また、消費者にとっては、新鮮で安全な食材を手に入れるだけでなく、農業への理解や地域コミュニティとのつながりが深まるメリットもあります。
農業人口の減少を食い止めることは容易ではありませんが、CSAは、地域農業の魅力を高め、新規就農者や若手農家を支える手段として期待されています。本記事では、最新の事例を交えながら、CSAが日本農業に与える可能性について詳しく解説します。
特徴は消費者による前払いシステム
CSAは、1986年のアメリカで、生産者と消費者が連携する活動として始まり、発展してきました。現在のアメリカでは、7000以上の農場でCSAが導入され、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ブラジル、中国、韓国等、約30ケ国以上へも広がりを見せています。CSAの正式名称である「Community Supported Agriculture」は、「地域支援型農業」と訳されますが、「Community」とは、既存の地域社会のことではありません。「農業には価値があり、農業を持続可能にする必要がある」といった考え方を共有できる生産者と消費者が、流通業者を介さず直接つながる団体と捉えるのが良いとされています。
一番の特徴は、消費者による前払いシステムです。消費者は、数ケ月あるいは一年といった期間、農場や都心部の拠点(カフェやマルシェ等)で定期的に受け取る農作物の代金を、契約時に前もって支払います。生産者は、その代金で種苗等を計画的に購入することができ、営農を安定させられるという仕組みです。

運営形態や実践方法に決まりはありません。様々な価値観に対応する多様なCSAが存在しています。運営形態は、一つの生産者と多くの消費者が協力して運営するところもあれば、複数の生産者がCSAを立ち上げるところ、消費者が運営し生産者に依頼するところ、運営会社が生産者と消費者を募集するところもあります。受け取り以外の交流、例えば、消費者による援農、農家が提供するイベント、直接話し合える意見交換会等々も盛んに行われ、お互いの理解を深めたり、関係性の維持を図ったりする仕組みが多く考えられています。

小規模有機農家へのメリット大
CSAが広がっている層は、有機栽培に価値を置く人たちです。日本の場合、高価になりがちな有機作物ですが、仲介業者を省くことで、消費者は新鮮で安心安全な作物をスーパーマーケット等より安価に、しかも定期的に入手可能となります。
有機栽培をする生産者は小規模事業者が多く、新規就農時は作物を上手く栽培できても、営業活動をする時間が持てなかったり、営業が上手くできなかったりするため、収入が安定しないことが多々あります。その場合、既存のCSAへ参加すれば、営業の負担が省け、栽培に集中することができるメリットがあります。
農業は、特に露地栽培では、天候の不順によって収穫量や価格が変動することから、生産者の収入が不安定になることがあります。CSAは、確実に買い手があることで一年間の収入を見込め、安定した農業を可能にします。消費者にとっては、収穫物に加え、収穫不良のリスクもシェアすることになるものの、農作業をせずとも農業を支えているという実感は、こういう点から得られるといえます。

地域・企業・教育機関の参加で広がるCSAの可能性
実は、CSAの源流は、日本の「産消提携(TEIKEI)」にあるといわれています。1970年代に誕生した産消提携は、生産者と消費者が顔の見える関係を築き、農産物を直接取引する仕組みとして始まりました。しかし、大きな広がりを見せることはなく、一部の団体でその理念が受け継がれるにとどまりました。CSAも、1990年代に導入されましたが、当初は十分な普及には至りませんでした。
しかし近年、SDGs(持続可能な開発目標)の認知拡大や農業後継者問題の深刻化を背景に、CSAが少しずつ注目されはじめたのです。若手農家や若手起業家がこの取り組みに参加する例が多く、さらに地域や企業、教育機関との連携により、これまで以上に多様な形で展開されるようになりました。
例えば、神戸市西区の「BIO CREATORS」は、生産に手間がかかるために価格が高くなりがちな有機野菜の販売法を模索するなかで、CSAの取り組みを始めました。一般消費者への販売だけでなく、意義に賛同する企業と契約し、従業員が職場で有機野菜を受け取れる「職場CSA」も実践しています。
奈良県曽爾村(そにむら)と近畿大学が連携して始まった「そにのわCSA」は、地域農業と教育の両面で注目される取り組みです。大学の学生や教職員がCSAの会員となり、地元農産物を定期的に購入することで、曽爾村の農家を支援しています。学生が地域住民や農家と交流することで、農業の現場を学ぶ機会にもつながっています。
中間支援者としてCSAの運営をサポートする例もあります。奈良市の八百屋「五ふしの草」は、若手農家がCSAに集中できるよう、会員の募集や販売を代行し、運営面の負担を軽減しています。また、農産物の供給が途切れた際には、他の農家から調達することで、会員に安定したサービスを提供しています。
福島県郡山市を拠点とする「あさかのCSA」は、農業と福祉を結びつけた「農福連携」が特徴です。地元農家と福祉施設が協力し、障がい者の就労支援を行いながら、消費者に新鮮な農産物を届けています。
CSAを通じて資源を循環させる取り組みを実践する「CSA LOOP」は、ビジネスの力でバランスの取れた優しい世界を目指す株式会社4Natureが始めました。消費者が家庭から出る生ごみを堆肥化し、それをCSAの生産者に提供。その堆肥を使って栽培された野菜が再び消費者のもとに届けられます。この循環の仕組みは、環境負荷を軽減するだけでなく、生産者と消費者が資源を通じて深い関係を築く新しい形として注目されています。
日本の普及には支援組織の存在が必要
このように、日本ではCSAが個人との関係を超えて、企業や地域、教育機関などともつながることで、徐々に広がりを見せてきています。しかし、その認知度はまだ十分に高いとはいえません。
東京工業大学の研究によると、CSAは新鮮な食材の提供にとどまらず、学びの機会や人々とのつながりといった豊かな体験を提供している点が、消費者の参加動機に大きく影響しているとしています。今後は、これらの魅力をいかに伝えられるかが重要です。そのためには、CSA全体を支援し、生産者、消費者の双方にメリットを啓蒙する組織の存在が必要です。たとえば、CSA発祥の地であるアメリカでは、「非営利団体Just Food」のような組織が、生産者と消費者をつなぐ仲介役として、情報提供や契約の促進、CSAの認証を行い、信頼性を高める役割を担っています。
CSAの価値を広め、生産者と消費者をつなぐ取り組みが進めば、地域農業の復興や食料供給の安定といった持続可能な農業の実現に寄与するでしょう。

また、CSAの継続には、生産者不足への対策も欠かせません。農業従事者の減少が進む中、新規就農者がスムーズに作業を始められる環境を整えることが重要です。トプコンは、新規就農者であっても熟練者と同じ精度で作業ができ、作業効率を上げられることを目指して、「農業の工場化」を掲げDXソリューションを提供しています。企業として、CSAの導入を希望する生産者の支えとなれる製品やソリューションに今後も取り組んでいきます。