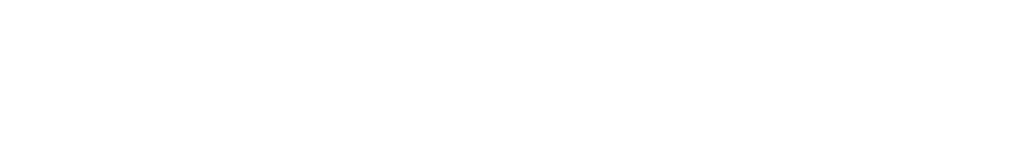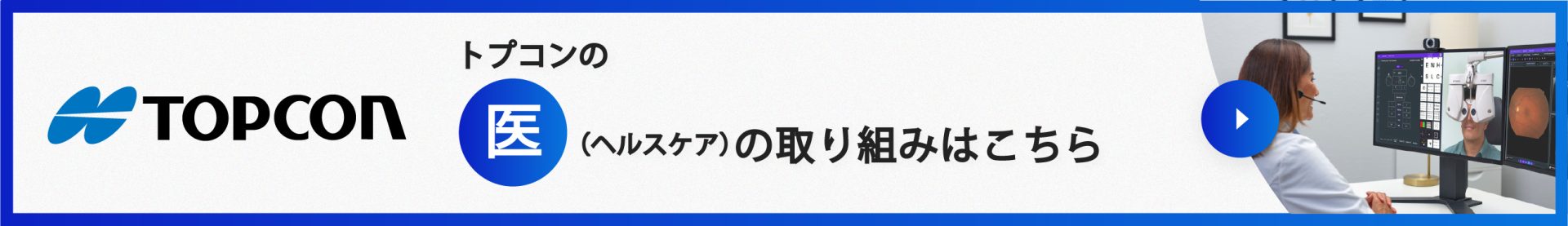目次
あなたには「アルコル」が見えていますか?
北斗七星は、その名の通り「北」の空にある「斗(中国語で柄杓)」の形をした「七」つの「星」です。比較的明るい星ばかりで見つけやすく、常に北の方角で輝く北極星を探すときの目印として習った人も多いでしょう。ミザールとアルコルは、天球上で極めて接近して見える二つの星「二重星」です。二重星は肉眼では通常一つの星に見えますが、ミザールとアルコルに限っては、視力に問題がなければ肉眼でも見分けることができます。都会では、街の光が明るくて不可能かもしれませんが、中世の空なら星ははっきり見えたはずなので、視力検査に使われることは理に適っています。アルコルが見えないということは、視力が悪いということ。見えていたアルコルが見えなくなった場合は、視力が落ちた可能性があります。
視力低下は老化のサイン

しかし、視力が落ちてきたことを知るための目安になる星だからといって、アルコルが「死兆星」や「寿命星」とまで呼ばれてしまうのはなぜでしょうか。それは、視力が年齢とともに変化することと関係しています。人間の目は赤ちゃんのときは、目の前で動くものが判別できる程度。2歳でも視力は0.3程度で、3歳ごろにようやく約6割が1.0に到達するそうです。これは、脳のなかの視覚野(見たものを分析する力)が発達したためだと考えられています。
つまり、赤ちゃんのときは、目は見えているけれどそれを分析する力がまだ身についていないため、視力に反映されないのです。一方、視覚野が発達して分析できるようになると、今度は加齢に伴って視力が低下していきます。40歳前後から老眼が始まり、50代の40〜50%が白内障を発症、80歳以上になるとほぼ100%の確率で白内障の症状が見られるようになります。老眼はピントを合わせる力が弱くなる現象で、白内障は目のレンズの役割をしている水晶体が白く濁る病気です。どちらも視力低下につながり、老化現象なので避けることができません。また、物を見るために最も敏感な部分である黄斑が変性してしまう「加齢黄斑変性症」や、老廃物を運び去る網膜静脈という血管が詰まる「網膜静脈閉塞症」といった病気など、加齢に伴い、視力低下の原因になる様々な病気を発症しやすくなります。
つまり、視力低下は老化のサイン。アルコルが見えなくなるまで視力が低下したことは、老化が進んでいるということ。寿命が近いと判断され「死兆星」や「寿命星」と言われるようになったのかもしれません。
アルコルはどれくらいの視力があれば見える?
現在の視力検査は、アルファベットのCのようなマーク(ランドルト環)を用いた視力表を利用するのが一般的です。ランドルト環は、19世紀後半〜20世紀初頭に活躍したフランスの眼科医・ランドルトにちなんで名付けられた世界共通の視力検査用の記号。上下左右のいずれかが開いていて、この隙間を見分けられるかどうかを検査します。隙間の両端の幅と眼の中心との間にできる角度を「視角」といい、視角の単位は1°の1/60である1’(分)で表します。そして、1’の視角が見分けられれば視力1.0と設定。「視力=1/視角」で計算し、視角が0.5’でも見分けられれば視力はその2倍の2.0。逆に視角が2’になるまで見えなければ視力は1/2の0.5になります。視力検査表では、通常5m離れたところから見たときの視力1.0のランドルト環が視角1’になるよう、隙間の幅は1.454 mm、ランドルト環全体の大きさは7.272 mmになっています。
それでは、アルコルとミザールは実際どれだけの視力があれば見分けられるのでしょうか。二つの星の見かけ上の距離は満月の半分程度で、角度でいうと約12’だそうです。視力を計算すると、1/12’=0.08。つまり視力が0.08以上あれば見えることになります。アルコルは四等星でミザールよりも暗いため、一概に視力が0.08あれば見えるとは言い切れませんが、星がよく見えた中世で、アルコルが見えない人は相当目が悪かったことは確か。メガネやコンタクトがない時代に生命の危機を感じることもあったでしょう。これが、死兆星と呼ばれるようになった本当の理由なのかもしれません。